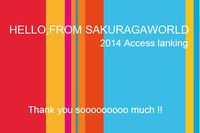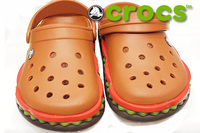2014年07月03日
「集団的自衛権」閣議決定!!…洗脳されないための新聞各紙見解比較

昨日、ついに安倍内閣が、集団的自衛権の行使を認めるために、憲法解釈を変える閣議決定をしました。
閣議決定というのは、行政の長である国務大臣全員の意思として、この法律案の承認を求めて国会に発議したということです。
もちろん、法律を作るのは国会ですから、いくら政府が閣議決定したところで、「何をふざけたこと言ってるんだ」となれば、これが法律になることはありません。
しかしながら、内閣=与党議員の代表であり、ネジレが解消して与党が圧倒的多数を持つ現在の政治情勢を考えれば、今回の閣議決定は、ほぼ間違いなく法律として成立することを意味します。
果たして、集団的自衛権の行使容認が、「専守防衛」(個別的自衛権)を貫いてきた戦後日本の安全保障政策にとって、大きな転換点を迎えることは間違いないわけですが、正直われわれ一般市民には、その中身がほとんど理解出来ていません。
極端な個別事例を挙げて「ね?必要でしょ?」と言われれば、「はぁ、確かに」と思うし、「これからは日本以外の国が攻撃された時にも、武力の行使が出来るようになるんだぞ?」と言われれば、なんだか戦争に加担することを認めるような不安も覚えます。

われわれが混乱する原因の一つには、メディア毎に言っていることがまったく違うということがあります。
片や「やっとまともな国になった」と言えば、もう一方では「軍隊容認へ動き出した」と言う。
賛成派のメディアの世論調査と、反対派のそれでは結果も全然違う。
メディアが国民の世論を作り上げていると言って過言でない現代にとって、これは非常に怖い気がします。
そこで本日は、大手5紙+地元紙がどういうスタンスで、この集団的自衛権行使容認の閣議決定を受け止めているのか、本日(7/2)の各紙の反応を掲載してご紹介してみたいと思います。
皆様が、今回の閣議決定に対してどのように考えるのか、その一助になれば幸いです。
まずは、全6紙のスタンスを図解してみます。

賛成派3紙、反対派3紙と、ちょうど半々となっていますが、まずは賛成派の新聞社から紹介してみます。



◇見出し
『集団的自衛権 限定容認』 (1面トップ)
「安保政策を転換」 (1面)
「首相 中国台頭を警戒 日米同盟さらに強化」 (2,3面)
「米評価 “平和に貢献”」「米艦隊運用に陸自入る」(2,3面)
「国際社会で存在感」「自衛隊 気引き締め」 (社会面)
◇社説 『真に国民を守るとは』
政府の集団的自衛権の行使容認は、日本の平和と安全を確かなものにする上で、歴史的な意義がある。
自公が歩み寄り、合意に達したことを歓迎したい。
「戦争への道を開く」といった左翼・リベラル勢力による情緒的な扇動は見当違い。自国の防衛と無関係に、他の国を守るわけではない。
政府・与党は秋の臨時国会から自衛隊法、武力攻撃事態法の改正など関連法の整備を開始するが、様々な事態に柔軟に対応できる仕組みにすることが大切だ。
PKOに限定せず、自衛隊の海外派遣に関する恒久法を制定することも検討に値する。


◇見出し
『「積極的平和」へ大転換』 (1面トップ)
「首相“今後50年 日本は安全だ”」 (1面)
「“助け合えぬ国”に決別を」「首相 悲願の改憲射程」 (2面)
「行使 法整備急ピッチ」 (3面)
◇社説 『21世紀の日本のかたち示す時』
長らく日本の安全保障政策を覆っていた「集団的自衛権」という“呪縛”から解き放たれた。その意義は大きい。
日米同盟強化のためには経済面ではTPP、安全保障面では集団的自衛権の解釈変更に伴う抑止力の強化を「車の両輪」として進めなければならない。
PKOで活動中の自衛隊が他国軍を助ける「駆けつけ警護」の問題などは以前から指摘されており、拙速な議論との批判は当たらない。


◇見出し
『集団的自衛権の行使容認』 (1面トップ)
「戦後の安保政策転換」 (1面)
「“72年政府見解”利用の結論は正反対に」
「解釈変更 整合性に腐心」 (2面)
「日米同盟強化で抑止力」 (3面)
「国どう守る 思い交錯」 (社会面)
◇社説 『助け合いで安全保障を固める道へ』
一部からは「海外での戦争に日本が巻き込まれかねない」といった不安も聞かれる。
しかし、日本、そしてアジアの安定を守り、戦争を防いでいくうえで、今回の決定は適切と言える。いまの体勢では域内の秩序を保ちきれなくなっているからだ。
米国の警察力が弱まった今、日本や韓国、オーストラリア、インド、東南アジアの国々が手を携え、アジア太平洋に協力網を作る。これを足場に中国と向き合い強調を保っていく。
安倍政権の議論の運び方に問題がなかったわけではない。閣議決定をここまで急ぐべきだったのか疑問だ。
さらに、実際の行使に当たり、「何を、どこまで認めるのか」といった事例毎の議論は、ほとんど深まらなかった。
これでは有権者の理解を得られないばかりか、不安が広がりかねない。
ただし、本日の社説のように、今回の閣議決定は急ぎすぎで、行使基準の熟議が必要とも言っています。
続いては、反対派の各紙を紹介してみます。



◇見出し
『9条崩す解釈改憲』 (1面トップ)
「海外で武力行使容認」「危うい“全て首相の意向”」 (1面)
「ねじ曲げられた憲法解釈」 「“自衛措置”強引に拡大」
「“戦後レジーム脱却”狙う」 (2面)
「危険はらむ軍事優先」 「周辺国との対立 更に刺激」 (3面)
「国会、歯止め役担えるか」 「賛成大多数、民意とずれ」 (4面)
「国民 守れるのか」 「不戦 叫び続ける」 (社会面)
◇社説 『「強兵」への道 許されない』
安倍政権が集団的自衛権行使を認めた7月1日は、日本の立憲主義の歴史において、最も不名誉な日として残るだろう。
国会に諮ることも、国民の意思を改めて問うこともなく、海外での武力行使に道が開かれた。
本誌世論調査では、多数は集団的自衛権行使に反対である。民意が国のあり方に根本的な変更を求めているとは、とても言えない。
それでもこの解釈改憲が実現したのは、政府・与党内の力学の結果である。
第一次世界大戦から今年で100年、ナショナリズムや軍事依存の危うさを反省する機運が、欧米を中心に高まっている。
そして、来年は戦後70年に当たる。そのときに日本の選ぶ道が「強兵」への復帰でよいはずはない。
「自衛隊が米軍を守るべき状況があったとしても、集団的自衛権は必要ない」と言い、「憲法解釈を見直してでも対応するほどの緊急性があるとは思えない」と主張しています。


◇見出し
『集団的自衛権 閣議決定』 (1面トップ)
「9条解釈を変更 戦後安保の大転換」「“限定”極秘の検討」 (1面)
「“自衛”拡大の懸念」 「防衛の隙間 意識」
「自公に“暗黙の了解”」 (2面)
「“明記”求めた首相」 「公明、楽観論で誤算」 (3面)
「野党 歯止め果たせず」 「賛否バラバラ」 (5面)
「自衛隊還暦の日 戦い死ぬリアル」 「“軍隊”へ変容始まる」(社会面)
◇社説 『歯止めは国民がかける』
遠い地での米国の軍事的劣勢も、イラクなどの中東情勢の混乱も、日米同盟の威信低下や国際秩序の揺らぎが「我が国の存立」にかかわると、時の政権は考えるかもしれない。
「国の存立」が自在に解釈され、その名の下に他国の戦争への参加を正当化することがあってはならない。
同盟の約束から参戦し、「自存自衛」を叫んで滅んだ大正、昭和の戦争の過ちを、繰り返すことになるからだ。
イラク戦争を支持した反省と総括もないまま、米国に「捨てられないため」集団的自衛権を行使するという日本の政治に、米国の間違った戦争とは一線を画す自制を望むことは、困難である。
閣議決定で行使を容認したのは、国民の権利としての集団的自衛権であって、政治家や官僚の権利ではない。
歯止めをかけるのも、国民だ。私たちの民主主義が試されるのはこれからである。


◇見出し
『集団的自衛権を容認』 (1面トップ)
「専守防衛逸脱の懸念」「拙速論議、国民置き去り」 (1面)
「自衛隊・米軍 進む一体化」「憲法9条改正を視野」 (2面)
「“戦後”幕引きに執念」「公明、深まる埋没感」 (3面)
「国民主権を軽視」 「論拠迷走 強引に決着」 (社会面)
「かすむ平和憲法」 「自衛隊員 揺れる思い」 (社会面)
◇社説 『国のありよう託せない』
戦後、憲法9条の下で歴代政権が積み重ねてきた「憲法上許されない」との解釈を捨て、自衛隊から「専守防衛」の制約を取り払って海外の前線に押し出そうとする安全保障政策の大転換だ。
しかし、そこに至るプロセスはあまりにも性急であり、乱暴というほかない。
この間、国民の理解と合意が顧みられることはなかった。同床異夢そのもので玉虫色の与党合意を支えにし、従来の憲法解釈から都合のいい部分をつまみ食いするなどて仕上げた閣議決定に、この国のありようを託す気にはとてもなれない。平和憲法にとって戦後最大の試練といえよう
憲法9条の空洞化も懸念しており、安全保障環境の変化に即した対応が必要と考えるなら、真っ正面から憲法改正を問うべきだと主張しています。
以上、今回の集団的自衛権の行使容認の閣議決定について、大手5紙と地元紙の見出しと社説を紹介してみました。
賛成派と反対派では、全く正反対の見解なので、ほんと混乱してしまいますね。
なかなか国際安全保障などというものは、われわれ一般人には難しい問題ですが、今回6紙に目を通して感じたのは、やはり拙速すぎるのではないか?ということでした。
個別の事例についてハッキリした見解もなく、「政府が発生した事態ごとに判断する」ではちょっと納得できません。
安倍総理は「これまでと変わらない」と何度もテレビで話していましたが、「私のさじ加減で安全にやるから大丈夫」を信用して良いものでしょうか?
国体に関わるものであればこそ、内閣が替わる度に、解釈が変わるようなものであってはならないと思います。
集団的自衛権の是非を問う前に、もう少し国民がわかるような説明と、更なる熟議が必要なのではないでしょうか?
みなさんはどう感じましたか?

昨日の閣議決定についての余波が続いています。
賛成派の急先鋒「産経新聞」の一面トップでは、昨日の朝日・東京2紙の報道について、名指しで非難しています。

朝日新聞や東京新聞の報道に対し、
国民の不安と危機感をあおり、世論を動かして自社の主張に政府を従わせようという手法は、もう見透かされているのではないか。
と指摘し、「日米同盟はこれまでと次元の異なる領域に入る。そのうち中国も『日本ともちゃんとうまくやりたい』と頭を下げてくるだろう」
今回の閣議決定を受け、ある外務省幹部はこう指摘した。主義・主張は各紙の自由だが、朝日、東京両紙ではこういう見解はまず読めない。
毎日も、かなり激しく今回の閣議決定には異議を唱えていたのですが、ターゲットはあくまで「朝日・東京」のようです。
これに対して、当の朝日や東京はといえば…

朝日新聞7月3日朝刊
朝日は、いまだ一面トップで大々的に閣議決定を批難しています。

東京新聞も一面トップで、集団的自衛権の行使容認は「先制攻撃」を認めたことだと指摘し、国民の半数以上は反対していると訴えています。
果たして、これらは「国民の不安と危機感をあおり…」なのでしょうか?
見透かされているのはどちらなのか…
まだまだ異論反論は収まりそうにありませんね。
ちなみに↓は、最近ネットで話題になっている、22年前の糸井重里氏による反戦コピーです。

なかなかシュールです。
大変遅くなりました。
確かに右左はよくわかりますねぇ。
政府よりか、反政府かとも言えますか。
ご指摘の常陽新聞…私は見ていませが、たぶんに右寄りではないかと…
 at 2014年07月29日 14:06
at 2014年07月29日 14:06