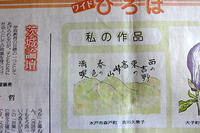2013年04月27日
一重の美学

天然記念物「大和桜」(山桜)
よくもまぁ桜の話ばかり書いているなぁ、と言われそうですが、4月は私にとっては桜月間。
まだまだ頭の中は桜のことでいっぱいなので、もうしばらくは続けようと思っています。
さて、例年だと県内ではGWが八重桜のピークとぶつかるんですが、今年はソメイヨシノ同様に開花が早く、既に散り始めているようです。
実は私はこの八重桜が苦手です。
明確な理由はないのですが、なんとなく異質な感じがしてしまうのです。
一葉や普賢象のような、清楚な印象の八重桜ならまだしも、関山のような派手なものになると、もはや桜としては見られません。

「関山(かんざん)」 「せきやま」とも呼びます
山桜の魅力に取り憑かれてからなのか、私の中の桜花観として元々あったのかはわかりませんが、「一重こそ桜」だという意識がどうしてもあるのです。
彼の兼好法師も『徒然草』の中で、
「家にありたき木は、松・桜。松は、五葉もよし。花は、一重なる、よし。八重桜は、奈良の都にのみありけるを、この此ぞ、世に多く成り侍るなる。吉野の花、左近の桜、皆、一重にてこそあれ。八重桜は異様のものなり。いとこちたく、ねぢけたり。植ゑずともありなん。遅桜、またすさまじ。」(第139段)
と書いています。

“兼好法師”こと吉田兼好
兼好法師の桜花観がよく表れていますが、ここには日本人の一重志向の美意識が見てとれます。
ちなみに、ここに書かれている「吉野の花」「左近の桜」は、いずれも山桜です。
そんな兼好法師の桜花観に対峙するのは太閤秀吉です。
実際には秀吉が八重を好んだとは言われていませんが、絢爛豪華を好んだ秀吉なら、たぶん八重志向であったことでしょう。
秀吉と桜というと、晩年の「吉野の花見」「醍醐の花見」が有名ですが、特に「醍醐の花見」は圧巻です。
まず花見のために醍醐寺の堂塔殿舎を修築、次に寺の馬場より槍山までの630mに近国の名花を植えさせ、三方院をベースに、ところどころの花園までの道には五色の緞子(どんす)の幔幕(まんまく)を打ち、招待客は北の政所や淀君以下、大名含め実に900人にも及んだと言います。

豊公吉野花見図屏風(左隻)
自己顕示欲が強く、派手好きな秀吉の「太閤一代の栄華これに尽きたりと言うべし」(山田孝雄「桜史」)な花見だったわけですが、私はこの対極にある、まさに秀吉の命によって切腹を言い渡された千利休の美意識を支持してしまう。
何度も書いていますが、山桜は花と同時に芽(葉芽)が出てきます。
1本1本花の形や色、咲く時期にも個性があり、同じ一重ではあっても、ソメイヨシノのように「群桜の圧倒的な景色」や「一斉に咲き一斉に散る」こともありません。
でも、八重桜やソメイヨシノにはない、千利休の「わび茶」に通ずる「美」がそこにはあると思うのです。
そんなところを感じとっていただければ、みなさんも山桜の魅力に気づいていただけるんじゃないでしょうか。
なんて、文化的素養のない男が言っても、あまり説得力がないんですけどね^^;
実は私はこの八重桜が苦手です。
明確な理由はないのですが、なんとなく異質な感じがしてしまうのです。
一葉や普賢象のような、清楚な印象の八重桜ならまだしも、関山のような派手なものになると、もはや桜としては見られません。

「関山(かんざん)」 「せきやま」とも呼びます
山桜の魅力に取り憑かれてからなのか、私の中の桜花観として元々あったのかはわかりませんが、「一重こそ桜」だという意識がどうしてもあるのです。
彼の兼好法師も『徒然草』の中で、
「家にありたき木は、松・桜。松は、五葉もよし。花は、一重なる、よし。八重桜は、奈良の都にのみありけるを、この此ぞ、世に多く成り侍るなる。吉野の花、左近の桜、皆、一重にてこそあれ。八重桜は異様のものなり。いとこちたく、ねぢけたり。植ゑずともありなん。遅桜、またすさまじ。」(第139段)
と書いています。

“兼好法師”こと吉田兼好
兼好法師の桜花観がよく表れていますが、ここには日本人の一重志向の美意識が見てとれます。
ちなみに、ここに書かれている「吉野の花」「左近の桜」は、いずれも山桜です。
そんな兼好法師の桜花観に対峙するのは太閤秀吉です。
実際には秀吉が八重を好んだとは言われていませんが、絢爛豪華を好んだ秀吉なら、たぶん八重志向であったことでしょう。
秀吉と桜というと、晩年の「吉野の花見」「醍醐の花見」が有名ですが、特に「醍醐の花見」は圧巻です。
まず花見のために醍醐寺の堂塔殿舎を修築、次に寺の馬場より槍山までの630mに近国の名花を植えさせ、三方院をベースに、ところどころの花園までの道には五色の緞子(どんす)の幔幕(まんまく)を打ち、招待客は北の政所や淀君以下、大名含め実に900人にも及んだと言います。

豊公吉野花見図屏風(左隻)
自己顕示欲が強く、派手好きな秀吉の「太閤一代の栄華これに尽きたりと言うべし」(山田孝雄「桜史」)な花見だったわけですが、私はこの対極にある、まさに秀吉の命によって切腹を言い渡された千利休の美意識を支持してしまう。
何度も書いていますが、山桜は花と同時に芽(葉芽)が出てきます。
1本1本花の形や色、咲く時期にも個性があり、同じ一重ではあっても、ソメイヨシノのように「群桜の圧倒的な景色」や「一斉に咲き一斉に散る」こともありません。
でも、八重桜やソメイヨシノにはない、千利休の「わび茶」に通ずる「美」がそこにはあると思うのです。
そんなところを感じとっていただければ、みなさんも山桜の魅力に気づいていただけるんじゃないでしょうか。
なんて、文化的素養のない男が言っても、あまり説得力がないんですけどね^^;
Posted by ug at 09:00│Comments(2)│サクラぐるひ
この記事へのコメント
ここで熱く語るug様のおかげで、たくさんの方々が山桜の魅力に気づかれたことでしょう(*^^)v
そしてまたug様にも、私をはじめきっとみなさん魅力を感じているはずです・・・ありがとうございます(^^)
そしてまたug様にも、私をはじめきっとみなさん魅力を感じているはずです・・・ありがとうございます(^^)
Posted by fairlady at 2013年04月27日 12:55
at 2013年04月27日 12:55
 at 2013年04月27日 12:55
at 2013年04月27日 12:55>>fairladyさん
あれ?熱く語っちゃってました?(´▽`;)ゞ
あまり山桜山桜言ってると、さすがに「もうわかったよ」ってことになりますね。
少し自重しよう^^;
たぶん、私には魅力はないと思いますが、桜がパワーを与えてくれているとは思います。
それよりも不二子ちゃんは誰の目にも凄く魅力的だとは思いますが(’-’*)
あれ?熱く語っちゃってました?(´▽`;)ゞ
あまり山桜山桜言ってると、さすがに「もうわかったよ」ってことになりますね。
少し自重しよう^^;
たぶん、私には魅力はないと思いますが、桜がパワーを与えてくれているとは思います。
それよりも不二子ちゃんは誰の目にも凄く魅力的だとは思いますが(’-’*)
Posted by ug at 2013年04月27日 17:29
at 2013年04月27日 17:29
 at 2013年04月27日 17:29
at 2013年04月27日 17:29コメントフォーム