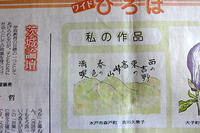2013年06月29日
引き続き葉っぱの話「陽葉と陰葉」

葉っぱの話になったので、ついでに葉っぱトリビアをひとつ。
学校の理科の授業で習ったのを覚えている人もいるかもしれませんが、本日はタイトルの通り「陽葉と陰葉」について書いてみたいと思います。
樹木が葉の光合成によって生育しているのは誰でも知っているかと思いますが、サクラのような広葉樹には、出来るだけ多くの光をとらえようと、幅の広い形をした葉が大量に(サクラの場合約5万枚~10万枚)付いています。
しかし、大量の葉を付けるが故に、自身の葉によってどうしても日陰になってしまうところが出てきてしまいます。
これに対処するために、樹木は日に当たる部分の葉と、日陰になってしまう部分の葉の構造を変えているのです。

日陰になる部分の葉を「陰葉」と呼びますが、この「陰葉」は日の当たる「陽葉」と比べて大きくて薄く、濃い緑色をしており(面積当たりの葉緑素が多い)、切れ込みが少ないのが特徴です。
また、ガス交換をするための穴(気孔)の数も1/2~1/4と少なく、その分気孔を開く反応速度が早く出来ているため、少ない光を有効に利用できるようになっています。
対する「陽葉」は明るい光の中でよく機能するように出来ています。
そのため呼吸速度(ガス交換)が早く、暗いところに置かれると生産するよりも多くの炭水化物を自分で消費してしまうため、段々やせ細ってついには枯れてしまうのです。

生育する環境に適応するために身につけた機能ですが、「陰葉」と「陽葉」の割合は当然生育条件に左右されます。
例えば、幼木の頃は周りの高い木に覆われてほとんど光を受けられないため、葉の全てが陰葉だったりします。
周りの木を追い抜くほどに育ってからはじめて陽葉が必要になってくるというわけです。
また、「陽葉」だった葉でも、周りの木々との折り合いや、自身の成長などで少しずつ日陰になっていくと、それに応じて「陰葉」に形を変えたりもします。
しかし、急激な変化には対応できず、周囲の木が切り倒されたり、剪定などで突然強い陽が当たるようになると、損傷を受けてしまうのです。
プランターなどで幼木を育てている時に、日向にあったものを、陽の当たらない場所に移動させると枯れてしまったりするのは、こうしたことからなんですね。
というわけで、本日も葉っぱの話でしたが、樹木を眺める機会がありましたら、是非こんなところにも注目してみてください。
樹木の見方が少し変わるかもしれません。
しかし、大量の葉を付けるが故に、自身の葉によってどうしても日陰になってしまうところが出てきてしまいます。
これに対処するために、樹木は日に当たる部分の葉と、日陰になってしまう部分の葉の構造を変えているのです。
日陰になる部分の葉を「陰葉」と呼びますが、この「陰葉」は日の当たる「陽葉」と比べて大きくて薄く、濃い緑色をしており(面積当たりの葉緑素が多い)、切れ込みが少ないのが特徴です。
また、ガス交換をするための穴(気孔)の数も1/2~1/4と少なく、その分気孔を開く反応速度が早く出来ているため、少ない光を有効に利用できるようになっています。
対する「陽葉」は明るい光の中でよく機能するように出来ています。
そのため呼吸速度(ガス交換)が早く、暗いところに置かれると生産するよりも多くの炭水化物を自分で消費してしまうため、段々やせ細ってついには枯れてしまうのです。

生育する環境に適応するために身につけた機能ですが、「陰葉」と「陽葉」の割合は当然生育条件に左右されます。
例えば、幼木の頃は周りの高い木に覆われてほとんど光を受けられないため、葉の全てが陰葉だったりします。
周りの木を追い抜くほどに育ってからはじめて陽葉が必要になってくるというわけです。
また、「陽葉」だった葉でも、周りの木々との折り合いや、自身の成長などで少しずつ日陰になっていくと、それに応じて「陰葉」に形を変えたりもします。
しかし、急激な変化には対応できず、周囲の木が切り倒されたり、剪定などで突然強い陽が当たるようになると、損傷を受けてしまうのです。
プランターなどで幼木を育てている時に、日向にあったものを、陽の当たらない場所に移動させると枯れてしまったりするのは、こうしたことからなんですね。
というわけで、本日も葉っぱの話でしたが、樹木を眺める機会がありましたら、是非こんなところにも注目してみてください。
樹木の見方が少し変わるかもしれません。
Posted by ug at 09:00│Comments(0)│サクラぐるひ
コメントフォーム