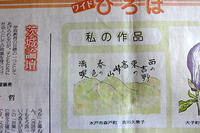2013年08月05日
真っ赤に紅葉している…

ご覧の桜の葉ですが、決して画像処理を施したものではございません。
昨日、公園の観察に出かけた時に見つけた霞桜の葉です。

このところの天候不順のせいでしょうか、秋と勘違いして紅葉が始まってしまったようです。
それにしても、芽吹きの赤芽とはまた違った真っ赤っか具合。
秋の霞桜の紅葉は、ここまで赤くはないんですけど…
せっかくなので、なぜ葉が紅くなるのか解説してみましょう。
桜のような日本の落葉樹は春に葉を出しますが、葉に含まれる葉緑素が太陽光のエネルギーを使って、取りこんだ空気中の二酸化炭素と、根から吸いあげた水を分解して、炭水化物(でんぷん)と酸素をつくっています。
これが光合成というものですが、この辺はもちろんみなさんご存知ですね。
さて、葉を作るにも維持するにも樹木にとってはエネルギーを必要とします。
それでも、夏の日照時間が長く気温が高い時期は、葉を維持するよりも葉が光合成をして作り出す栄養の方が大きいため、例えば葉の活動に7割の栄養が使われても、残り3割が樹木自体に回ってくるので、割が合うわけです。
投資と回収を考えていただければわかりますね。
しかし、秋になり日照時間が短く気温が下がってくると、これ以上投資しても回収は難しいと樹木が判断します。
そうすると、葉の中にあるタンパク質や葉緑素といった再利用される物質が分解され、樹木に戻されていきます。
(このときが一番樹木が生長する=太る)
このとき、まだ葉にはシリコンや塩素、重金属と言った樹木には不必要な物質も残っています。
言ってみれば葉は、廃棄物の捨て場のようなもので、これを切り離すことでゴミを外部に放出しているのです。
こうして葉緑素が抜けていくと、葉緑素に隠れていた黄色の色素(カロチノイド)が表に透け出てきます。
この現象は、バナナやみかんが熟して行く過程と同じです。
こうして「黄葉」が起こるわけですが、枯れかかっている葉の中では残っている糖類から大量の赤色色素(アントシアニン)が作られます。
これが異なった割合の黄色色素と混ざって、橙色や赤色の「紅葉」となるというわけです。

まるで赤い実がなっているようです
今回のこの霞桜の紅葉は、色から見ても相当アントシアニンが働いているようですね。

紅葉した葉は落葉してしまいます
それにしても、今年の気候はちょっと変です。
桜に…いや、農作物に大きな被害が出ないことを祈っています。
Posted by ug at 08:00│Comments(0)│サクラぐるひ
コメントフォーム