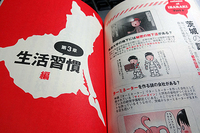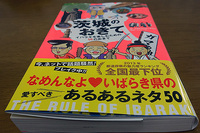2013年11月10日
大規模津波・地震防災総合訓練に行ってきた
本日、国土交通省、茨城県、ひたちなか市、笠間市の主催による、「平成25年度 大規模津波・地震防災総合訓練」が実施されました。
東日本大震災からの復旧が現在も続く中、これを教訓として…とお思いでしょうが、実はこの訓練は平成16年のスマトラ島沖地震が契機となって毎年実施されているものです。
とはいえ、県民の防災意識は、先の東日本大震災から急激に高まったことは間違いなく、今回は、この時の教訓から、国土交通省主催の「大規模津波防災総合訓練」と、茨城県主催の「平成25 年度茨城県・笠間市総合防災訓練」を合同で実施する形となりました。
よって、主に津波に対する防災訓練をひたちなか市の常陸那珂港で、大地震による防災訓練を笠間市の芸術の森公園でと、2か所で同時に実施されることになったというわけです。
県の発表によると、メイン会場のひたちなか市で約6000名、笠間会場で約3700名と、参加人員だけ見ても相当な規模の訓練であることがわかります。
そんな防災訓練を見に、サブ会場である笠間芸術の森公園に出かけてまいりました。

笠間会場の訓練進行表
会場に到着するや目に飛び込んできたのは、会場中央に設置された、電車やビル、倒壊した家屋や車のセットです。

やや雑な作り(?)の水戸線らしき電車のセット

倒壊した家屋のセット

横転した車も
9時から予定されていた訓練は、東日本大震災の時を思い出す、緊急地震速報の放送で始まりました。
私のスマホも緊急速報の着信音が鳴り、画面を見ると「これは防災訓練です…」の文字が映し出されておりました。
まずは、住民の避難(トップ画像)、初期消火などの訓練です。

住民によるバケツリレーの訓練
この間、航空自衛隊の偵察機や、偵察用のヘリが飛んできたり、県警の白バイ隊(?)が、オフロードバイクで被害状況の確認のため、がれきを乗り越える訓練も行われています。

難なくU字溝を乗り越える隊員
そうこうするうちに、いよいよメインともいうべき、救援・救護の訓練が始まりました。

右手にいる方達は「がんばれー!!」と負傷者に声を掛けています
先ほどの電車内で負傷した人や、ビルに取り残された人たちの救助が開始されます。

ビルの上から搬送される負傷者
ここでは、消防署や警察、自衛隊、赤十字…と、関係機関の方達が連携して救援にあたっていました。
やがて、辺りに救急車やレスキューのサイレンがけたたましく鳴り響くと、「こんなに集めちゃって大丈夫なの?」と思うほど(15台ほど)の救急車が、まるでパレードのように集まってきました。

救護本部には、DMATと呼ばれる医師、歯科医師、看護師、薬剤師などが集まり、負傷者の手当にあたっています。

緊急を要する重傷者のために、いよいよドクターヘリも到着しました。

このあとひたちなか会場に飛んでいったようです
関係機関の方達は与えられた任務を確実にこなしているようでしたが、会場全体を見るとそこはやはり訓練、市民の参加者や見学者はアトラクションを見ているような感じでした^^;

開始早々は、ほとんど関係者ばかりで、一般の見学者の姿は見られなかったのですが、飛行機やヘリ、先ほどの訓練の緊急地震速報などを見て駆け付けたのでしょう、1時間ほど経った頃には子ども連れの姿なども見られるようになってきました。

そんな一般の方達のために、会場には展示・体験・普及啓発のためのブースが設けられており、こちらは関係者含め盛況でした。


関係機関の啓発ブース

AEDの使い方や心肺蘇生を学べるブース

おなじみ「地震体験車」…東日本大震災でリアルに体験してますけどね^^;

消化器による消化体験
展示車両も何台か並んでいます。

「移動変圧器」…6万ボルトを6千ボルトに変圧できるそうです

基地局がダウンした時のための移動基地局(auとSoftBankが来ていました)

県の所有するオフロード車「メガクルーザー」…格好いい^^;

DoCoMoは充電サービスと災害伝言板サービスの紹介をしていました
災害対策グッズなどを売るブースもありました。

ホームセンター「コメリ」の災害グッズ展示販売ブース

“災害に強い”ガス設備の展示ブース

伊藤園の手動で発電する自販機
また、婦人防火クラブのみなさんが、豚汁を無料で配ってくれる「炊き出し訓練」ブースもあり、

私もしっかりごちそうになってきました。

寒かったので、ほんっとうに美味しかったです
会場では、この後ライフライン復旧の訓練や、大規模火災対応の訓練などが行われたようですが、私は次の予定のために救助まで見て会場を後にしました。
とまぁ、大まかに防災訓練の様子をご紹介したわけですが、確かに大がかりな訓練だなぁという印象は受けました。
メイン会場の常陸那珂港では、もっと大がかりな訓練が行われたようですので、そちらも見てみたかった気もします。
岩手県釜石市の例を出すまでもなく、日頃の訓練によって助かる命もあるわけで、こうした取り組みの重要性は東日本大震災でみんな理解していると思います。
ただ、今回の防災訓練は、やはり関係機関の方達のためといった感が強く、一般市民にどれだけ伝わっているかは疑問に思いました。
地震が来たらどういう行動を取るのが良いのか、避難場所は?…等々、地域毎に啓発・普及するような取り組みも必要ではないでしょうか?
そういう一般市民向けのコーナーがなかったことが、ちょっと残念な気がしました。
以上、「平成25年度 大規模津波・地震防災総合訓練」のご報告でした。
※11/10追記
本日の新聞によると、笠間会場はやはり負傷者の救助の優先順位を決める「トリアージ」訓練が主だったようです。
ていうか、ほとんど本会場であるひたちなか会場の話題ばかりでしたね^^;
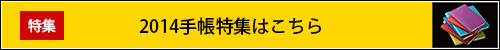
よって、主に津波に対する防災訓練をひたちなか市の常陸那珂港で、大地震による防災訓練を笠間市の芸術の森公園でと、2か所で同時に実施されることになったというわけです。
県の発表によると、メイン会場のひたちなか市で約6000名、笠間会場で約3700名と、参加人員だけ見ても相当な規模の訓練であることがわかります。
そんな防災訓練を見に、サブ会場である笠間芸術の森公園に出かけてまいりました。
笠間会場の訓練進行表
会場に到着するや目に飛び込んできたのは、会場中央に設置された、電車やビル、倒壊した家屋や車のセットです。
やや雑な作り(?)の水戸線らしき電車のセット

倒壊した家屋のセット
横転した車も
9時から予定されていた訓練は、東日本大震災の時を思い出す、緊急地震速報の放送で始まりました。
私のスマホも緊急速報の着信音が鳴り、画面を見ると「これは防災訓練です…」の文字が映し出されておりました。
まずは、住民の避難(トップ画像)、初期消火などの訓練です。
住民によるバケツリレーの訓練
この間、航空自衛隊の偵察機や、偵察用のヘリが飛んできたり、県警の白バイ隊(?)が、オフロードバイクで被害状況の確認のため、がれきを乗り越える訓練も行われています。
難なくU字溝を乗り越える隊員
そうこうするうちに、いよいよメインともいうべき、救援・救護の訓練が始まりました。
右手にいる方達は「がんばれー!!」と負傷者に声を掛けています
先ほどの電車内で負傷した人や、ビルに取り残された人たちの救助が開始されます。
ビルの上から搬送される負傷者
ここでは、消防署や警察、自衛隊、赤十字…と、関係機関の方達が連携して救援にあたっていました。
やがて、辺りに救急車やレスキューのサイレンがけたたましく鳴り響くと、「こんなに集めちゃって大丈夫なの?」と思うほど(15台ほど)の救急車が、まるでパレードのように集まってきました。
救護本部には、DMATと呼ばれる医師、歯科医師、看護師、薬剤師などが集まり、負傷者の手当にあたっています。
緊急を要する重傷者のために、いよいよドクターヘリも到着しました。
このあとひたちなか会場に飛んでいったようです
関係機関の方達は与えられた任務を確実にこなしているようでしたが、会場全体を見るとそこはやはり訓練、市民の参加者や見学者はアトラクションを見ているような感じでした^^;
開始早々は、ほとんど関係者ばかりで、一般の見学者の姿は見られなかったのですが、飛行機やヘリ、先ほどの訓練の緊急地震速報などを見て駆け付けたのでしょう、1時間ほど経った頃には子ども連れの姿なども見られるようになってきました。
そんな一般の方達のために、会場には展示・体験・普及啓発のためのブースが設けられており、こちらは関係者含め盛況でした。

関係機関の啓発ブース
AEDの使い方や心肺蘇生を学べるブース
おなじみ「地震体験車」…東日本大震災でリアルに体験してますけどね^^;
消化器による消化体験
展示車両も何台か並んでいます。
「移動変圧器」…6万ボルトを6千ボルトに変圧できるそうです
基地局がダウンした時のための移動基地局(auとSoftBankが来ていました)
県の所有するオフロード車「メガクルーザー」…格好いい^^;
DoCoMoは充電サービスと災害伝言板サービスの紹介をしていました
災害対策グッズなどを売るブースもありました。

ホームセンター「コメリ」の災害グッズ展示販売ブース
“災害に強い”ガス設備の展示ブース
伊藤園の手動で発電する自販機
また、婦人防火クラブのみなさんが、豚汁を無料で配ってくれる「炊き出し訓練」ブースもあり、
私もしっかりごちそうになってきました。
寒かったので、ほんっとうに美味しかったです
会場では、この後ライフライン復旧の訓練や、大規模火災対応の訓練などが行われたようですが、私は次の予定のために救助まで見て会場を後にしました。
とまぁ、大まかに防災訓練の様子をご紹介したわけですが、確かに大がかりな訓練だなぁという印象は受けました。
メイン会場の常陸那珂港では、もっと大がかりな訓練が行われたようですので、そちらも見てみたかった気もします。
岩手県釜石市の例を出すまでもなく、日頃の訓練によって助かる命もあるわけで、こうした取り組みの重要性は東日本大震災でみんな理解していると思います。
ただ、今回の防災訓練は、やはり関係機関の方達のためといった感が強く、一般市民にどれだけ伝わっているかは疑問に思いました。
地震が来たらどういう行動を取るのが良いのか、避難場所は?…等々、地域毎に啓発・普及するような取り組みも必要ではないでしょうか?
そういう一般市民向けのコーナーがなかったことが、ちょっと残念な気がしました。
以上、「平成25年度 大規模津波・地震防災総合訓練」のご報告でした。
※11/10追記
本日の新聞によると、笠間会場はやはり負傷者の救助の優先順位を決める「トリアージ」訓練が主だったようです。
ていうか、ほとんど本会場であるひたちなか会場の話題ばかりでしたね^^;
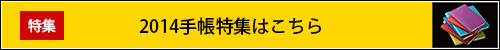
Posted by ug at 01:45│Comments(0)│ちいき
コメントフォーム