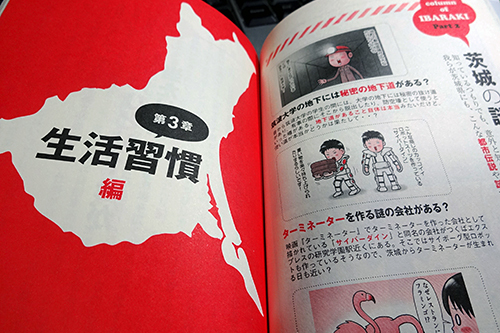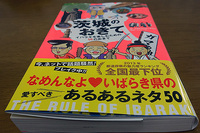2014年08月13日
なめんなよ♡いばらき…『茨城のおきて』を検証してみた(後編)

18 車はひとり1台が当たり前
 仕事も買い物も、車がなければどうにもならない農村部などでは、「軽トラ」というセカンドカーもあるので、家によってはひとり1台を超えているかもしれません。
仕事も買い物も、車がなければどうにもならない農村部などでは、「軽トラ」というセカンドカーもあるので、家によってはひとり1台を超えているかもしれません。軽トラでなくても、軽自動車が異常に多いのも特徴でしょうか。
まだおばあちゃん世代の女性の免許取得率が低いので、実際はそこまでではないでしょうが、これがもう10年もすると、確実にひとり1台の時代がやって来るのではないかと思います。
ちなみに、都道府県データランキングによると、平成24年の「自家用車普及率」は、群馬県がトップで、2位が栃木、3位が茨城と北関東3県で熾烈なトップ争いをしています。
信憑性 ★★☆
19 電車で飲み食いしているのは普通の光景
 昔から夜の常磐線の酒臭さは有名でした。
昔から夜の常磐線の酒臭さは有名でした。お酒を飲んで帰宅するサラリーマンもいますが、さきいかをつまみにプシュッと缶ビールを開ける光景は確かに普通でした。
しかし、それも常磐線がボックス席だった時代の話で、今のようにベンチシートになってからはほとんど見かけなくなりました。
でもこれ、決して茨城だけの話ではないと思います。
新幹線では車内販売もあり、飲食は当たり前だし、同じように宇都宮線だってプシュッとやる人はいます。
だって、特急のホームじゃなくてもKIOSKには缶ビールやつまみが売られているんだからしかたないでしょ。
信憑性 ★★☆
22 「七五三」が豪華すぎる
 鹿行地区にある親戚の七五三で、うちの両親が結婚式場での豪華なお祝いに出席した事がありました。
鹿行地区にある親戚の七五三で、うちの両親が結婚式場での豪華なお祝いに出席した事がありました。これまでそんな七五三祝いなど経験したことのない両親は、驚いた様子で、新郎新婦のように高砂に子どもが座ったり、ケーキ入刀をしたり、キャンドルサービスをしたり、最後にはおじいちゃんおばあちゃんに花束贈呈までした様子を興奮気味に話していたのを覚えています。
ほぼ結婚式状態の宴会に、お祝いを(金額を上げて)包み直し、途中で子どもに「おひねり」まであげる余興もあったりで、かなりの出費になったとも話していました。
茨城ではこういうのを「豪華」ではなく、「派手」と言います。
しかしこれも、ごく一部の話ですよ。
「派手にやる人もいる」ってだけで、みんながみんなホテルや結婚式場でお祝いをするわけではありません。
ていうかこれ、少子化の中で婚礼をするカップルの数が減っている中、利益を維持するためにホテルや結婚式場が必死に七五三市場を開拓した結果でしょう。
信憑性 ★☆☆
24 全国で唯一地元テレビ局がない県なのが悲しい
 実は生まれてこの方地元にテレビ局のないことが当たり前なので、特に「悲しい」と思うこともなかったりします。
実は生まれてこの方地元にテレビ局のないことが当たり前なので、特に「悲しい」と思うこともなかったりします。東北などと違い、一応東京と変わらないチャンネル構成なので、不便も感じませんし。
2011年までは早起きすればフジテレビで『おはよう茨城』なんて番組も見られましたが、私の周りでわざわざ早起きしてこれを見ているという人を聞いたことがありません。
最近は地デジのおかげで、ニュース程度ですが県域放送もあるし、県が運営するインターネットテレビ『いばキラTV』もあります。
『いばキラTV』もだいぶコンテンツが充実してきたようですし、ローカル番組が見たいなら不自由はないと思います。
「ローカルテレビ局がなくて…」と他県の人に自虐ネタとして話すことはあっても、それを本気で嘆いている人はほとんどいないのではないでしょうか。
信憑性 ★☆☆
25 長男は「消防団」へ入るのがお約束
 茨城の成人男性にとって「消防団」は最強の優先力を持つ活動である。
茨城の成人男性にとって「消防団」は最強の優先力を持つ活動である。などと大げさに書かれていますが、これも昔日の話ですね。
昔は実家の商売を継いだりすれば、それは間違いなく「入れ」と言われました。
「青年団」亡き後、地域の“後継ぎ”同士の交流の場として「消防団」がそれを担っていました。
しかし、今や地域の商店街は消え失せ、ほとんどの分団がサラリーマン中心の団員で構成されています。
よって訓練等の行事は土日になり、平日昼間の火災に果たして何人が出動できるのか…
いまだに会社や他の団体では出来ない“濃い”飲み会や旅行は健在のようですが、「最強の優先力」ではなくなっています。
信憑性 ★☆☆

29 名物は納豆だけじゃない「レンコン」の50%は茨城産!
 北海道に次いで、茨城は農産物出荷額全国2位だということはご存じでしょうか?
北海道に次いで、茨城は農産物出荷額全国2位だということはご存じでしょうか?県全体の面積に占める耕地面積の割合は29%と、こちらはずっと全国1位だったりします。
日本を代表する「農業県」というわけです。
にもかかわらず、「特産品」と呼ばれるものが、全然知られていない。
そんな特産品の一つがレンコンなわけですが、有名なところではメロンや栗も全国1位です。
他にも陸稲、春はくさい、春レタス、ピーマン、夏ネギ、春秋なす、ちんげんさい、水菜なども収穫量全国1位なんです。
ブランディングやPRがいかに下手かがわかります。
こうしたところが決して立地や資源に恵まれているわけではないのに、「魅力度全国ワースト1位」になってしまう理由なのではないでしょうか。
良いように解釈すれば、恵まれている地域だから、必死になってブランドを作る必要もないってことかもしれません。
信憑性 ★★★
30 「牛久大仏」も大きいが家も大きい
 映画『下妻物語』で一躍有名になった牛久大仏ですが、実は下妻からは相当遠い場所にあったりします。
映画『下妻物語』で一躍有名になった牛久大仏ですが、実は下妻からは相当遠い場所にあったりします。圏央道の開通や「阿見プレミアムアウトレット」ができたおかげで、知名度も上がってきているようです。
さて、問題は「家が大きい」というところ。
実は、数字的に見ると、家が大きいわけではなくて、住宅の敷地面積が広い(全国1位)ということなんですね。
これは↑の農業県という部分と関係があるんですが、農家率の高さも日本一なので、必然的に敷地も広くなるわけです。
もうひとつ関係するのは、関東平野の外れということもあり、県北の一部を除けばほぼ平地で、お隣栃木と比べても、居住可能面積が広いところ。
裏を返せば住民が分散して暮らしているので、特に人口が集中することがなく、4、5万人の中途半端な自治体が多いということでもあります。
信憑性 ★★☆
34 地味な「日本三大○○」ばっかり
 笠間稲荷は「日本三大稲荷」、偕楽園は「日本三大名園」、袋田の滝は「日本三大名瀑」などと呼ばれる(呼ぶ?)ようですが、確かにいずれもやや地味です。
笠間稲荷は「日本三大稲荷」、偕楽園は「日本三大名園」、袋田の滝は「日本三大名瀑」などと呼ばれる(呼ぶ?)ようですが、確かにいずれもやや地味です。「三大…」に限らず、昔からある茨城の観光資源は全国に名だたるというものがないですね。
アトラクションも、「国営ひたち海浜公園」のあれでは地味すぎるし、つくば研究学園都市の「つくばエキスポセンター」やJAXAをはじめとする施設見学も、サイエンス好きの子どもには良いかもしれませんが、誰もが楽しいというわけでもありません。
そこそこのものはたくさんあるのに、誰にも勧められるスポットがないというのは、やはりちょっと悲しい気がします。
そこが「魅力度ワースト1位」の要因でもありますが…
信憑性 ★★★
38 なんだかんだで「つくば万博」の思い出を引きずっている
 これは「ないわぁ」ですね。
これは「ないわぁ」ですね。30年近く経った今、万博に相当入れ込んで通った人とか、運営に何らかの関わりがあった人とかでない限り、もはやEXPO '85(つくば科学万博)が会話に出てくるようなこともないと思います。
これを機につくば研究学園都市から、つくば市へ、そしてTXの開業による沿線全体の発展があると考えれば、確かにその意義は大きいですが、パビリオンやイベント自体の思い出なんて、ほとんど忘れてしまっています。
当時、多感な子どもだった世代には、今も強く思い出として残っているのかもしれません。
信憑性 ★☆☆

43 平成の大合併でできた「つくばみらい市」はどうかと思っている
 今では平成の合併で生まれた新市名にも、あまり違和感を感じなくなってきましたが、やはり当初は結構「???」と思うような名前もありましたね。
今では平成の合併で生まれた新市名にも、あまり違和感を感じなくなってきましたが、やはり当初は結構「???」と思うような名前もありましたね。著者には「つくばみらい市」に違和感があったようですが、私は隣の「筑西市」に一番違和感を覚えました。
本書ではわが「桜川市」も、県南の稲敷郡にあった「桜川村」をパクったと書いていますが、こちらとしては対角線にある遠~い桜川村の存在感が薄すぎて、そんなことを考えもしませんでした。
おもしろいと思ったのは、「ひたちなか市」が、「日立市や那珂市と隣接するのに混乱するだろ!!」、とツッコまれていたということ。
ひらがななのであまり感じませんでしたが、確かにまるで日立市と那珂市が合併したような市名です。
また、「つくば市」「つくばみらい市」「筑西市」の“つくば系”3市と、「日立市」「ひたちなか市」「常陸太田市」「常陸大宮市」の“ひたち系”4市が訪問者を戸惑わせるという解説もなるほどと思いました。
信憑性 ★★★

48 「茨城弁は怒っているみたい」と言われがち
 これはもう定説なので異論はないのですが、最近はU字工事の影響で栃木弁に負けている気がしないでもありません。
これはもう定説なので異論はないのですが、最近はU字工事の影響で栃木弁に負けている気がしないでもありません。それよりも、インターネットを「エンターネット」、イバラキを「エバラギ」、靴下を「グヅシタ」と言うなどと書いていますが、これはないでしょう。
おばあちゃんおじいちゃんでも「クヅシタ」とは言いますが、「グヅシタ」はないです。
ま、地域でも全然違うし、茨城弁について語り出すと「茨城王」のように1冊の本が書けるので、あまりツッコミは入れません。
解説につい肯いてしまったのは、「橋」と「端」と「箸」がすべて同じイントネーションだということ。
私も都内在住の頃、「朝」と「麻」の違いが言えず恥ずかしい思いをした記憶があります。
とりあえず、東京で堂々と話すのは恥ずかしい部類の方言であることに間違いはないでしょう。
信憑性★★★
50 千葉とひとくくりにされるのはイヤ 群馬・栃木と一緒にされるのはもっとイヤ
 その昔は「ぐんたまちばらぎ」と、関東の田舎をバカにして呼んだりしていましたが、今や埼玉は完全に抜けだし、千葉は東京ディズニーランドの効果もあり、北関東3県の上位に位置するのは間違いないでしょう。
その昔は「ぐんたまちばらぎ」と、関東の田舎をバカにして呼んだりしていましたが、今や埼玉は完全に抜けだし、千葉は東京ディズニーランドの効果もあり、北関東3県の上位に位置するのは間違いないでしょう。よって「ちばらぎ」と呼ばれて「イヤ」と思うのは、たぶんに千葉の方ではないかと思います。
とはいえ、確かに群馬・栃木にはライバル心もあり、一緒にされるのにはちょっと抵抗を感じます。
でもなぜかU字工事を応援してしまうのは、実は群馬や栃木に、同じ北関東という同郷心があるのだと思います。
信憑性 ★☆☆
以上、2回に分けて『茨城のおきて~イバラキを楽しむための50のおきて』の中から、気になったものを私的に検証してみました。
世代や地域で、受け止め方は変わると思いますが、読んでいてなかなか楽しい本でした。
興味のある方はご一読を。

『茨城のおきて~イバラキを楽しむための50のおきて』
コメントフォーム