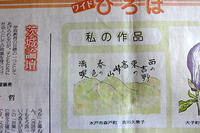2014年03月15日
たぶん日本人の99%はソメイヨシノすらもよくわかっていない

「桜川のサクラ」はヤマザクラです。
こう言っても、何のことやらサッパリわからないという方がほとんどでしょう。
「開花予想」や「サクラ前線」が、「ソメイヨシノ開花予想」と、「ソメイヨシノ前線」であることを見ても、現代の日本人にとってサクラといえば、それはソメイヨシノを指すのが一般的です。
現在関東でも満開を迎えている「河津桜」や、「三春の滝ザクラ」に代表される「しだれ桜」、関東ではGWあたりに満開を迎える「八重桜」など、ソメイヨシノ以外の話題も時おり伝わっては来ますが、それらはあくまで「サブステージ」のはなし。
また、そうした桜が果たしてどういった品種で、どういう特徴を備えたものなのかわかっている人もほとんどいません。
「桜とくれば花見の宴会だ」という、大多数の日本人にとって、正直桜の品種などどうでも良いのかもしれません。
春の訪れを告げる、ソメイヨシノのあの圧倒的な群桜の華やかさを目にすれば、誰だって気分が高揚して、宴席のひとつも催したくなるものです。
自生のヤマザクラの魅力を伝えたい…
と思いながら、実のところ日本人の抱く桜のイメージが、ソメイヨシノの群桜として定着してしまった現代において、それはたぶん無理だろうなという諦めもあり、昨日の記事となりました。
ごく一部の専門家やマニアと言われるような人間でなければ、興味を持たれることもないでしょう。
なにせ、ソメイヨシノすらよく知らないという人がほとんどなのですから…^^;
そこで、今となってはマニアックなヤマザクラの話しはひとまず置いといて、現代の日本人にとっての桜=ソメイヨシノについて、しばし解説してみようと思います。
ソメイヨシノという桜を知ることで、他の桜にも、もしかしたら自生種の桜にも関心をもっていただけることを期待して…

ソメイヨシノの起源については諸説ありますが、最も有力な説は、江戸末期に江戸染井村(現在の豊島区駒込)の植木職人が、園芸品種として作出したというものです。

染井之植木屋(絵本江戸桜) 北尾政美画 1803(享和3)年
日本に9種類ある自生種(野生の桜)の中の、「江戸彼岸(エドヒガン)」という桜と「大島桜(オオシマザクラ)」という桜の交配によってできた桜ですが、江戸彼岸の特徴である「葉より先に花が咲く」ところ、大島桜の「花が大きい」ところを受け継ぎ、更に花付きが非常に良い(1つの枝に付く花の数が多い)と、見事な優性遺伝で生まれた桜です。
当初は、日本一の桜の名所として有名な「吉野山」の名前を冠した「吉野桜」として売り出されました。
「東京にいながら吉野の桜が見られる」という触れ込みで売り出したわけです。
この売り方が大ヒットとなり、「吉野桜」はまたたくまに江戸の街を覆っていきます。
江戸の三代桜の名所として知られた、上野、飛鳥山、向島は、いずれもヤマザクラを取り寄せて植えられたものでしたが、明治になると「吉野桜」に侵略されていきます。

「江戸名所百景」上野清水堂不忍ノ池 (この頃はまだヤマザクラがほとんど)
しかし、上野精養軒前の「吉野桜」の並木が、吉野山のヤマザクラと違う品種だと気づいた役人がいて、混乱を避けるためにその後(明治33年)「吉野桜」は「染井吉野」へと改名され、日本園芸雑誌に発表されます。

なぜか今も売られている「吉野桜」…たぶん大島桜系のもの(2008年靖国神社にて)

あまり知られていませんが、ソメイヨシノが爆発的に普及した背景に、この時期(明治初頭)の桜の伐採があります。
江戸末期には、大名屋敷や寺社などにヤマザクラをはじめとする多様な品種の桜が植えられていました。
しかし、明治維新となり、大名屋敷が荒廃すると、その庭に植えられていた桜や、廃仏毀釈のあおりを受けて、寺社に植えられていた桜が次々に伐られていきます。
その後、そうした場所に代わりに植えられていくのは、もちろん数百本から千本単位のソメイヨシノでした。
見た目の華やかさもありますが、ソメイヨシノはクローンということもあってか、他の桜に比べて非常に成長が早いという特徴もあります。
また、土質を選ばないという管理のしやすさもあって、出来るだけ早く見事な花が見たいという人々にとって、これほど便利な桜はなかったわけです。

更にソメイヨシノの普及に拍車を掛けたのは、近代化を急ぐ日本にとって欠かせない軍隊の拡充でした。
全国各地に配置された連隊の敷地には、決まってソメイヨシノが植えられました。
散り際の潔さから「軍国の花」として、これを積極的に利用したのです。

靖国神社「遊就館」
『同期の桜』をはじめ、桜が使われた軍歌も多くみられるように、ソメイヨシノは国家と運命を共にする精神の象徴となっていきました。
そして、戦に勝つ度に「戦勝記念」としてまた植えられていくのです。

靖国神社には戦友会の植えた桜が多数見られる
第二次世界大戦の終戦から今年で69年を迎えようとしていますが、各地の駐屯地にソメイヨシノの古木が多く見られ、いずれも花見の名所となっているのには、こうした背景があったのです。

その後の日本は戦後の高度経済成長時代を迎えますが、好景気に沸く日本の「花見」は飲めや歌えの宴会が主流となっていきます。

靖国神社の花見風景…靖国の桜の謂われを知る人は少ないでしょう
こうした花見の名所づくりに、こぞってソメイヨシノが植えられたのは言うまでもありません。
明治~大正~昭和という激動の時代、特に高度経済成長時代の日本を象徴する桜は、ソメイヨシノ以外に考えられなかったでしょう。
こうして、たった1本の木から作られたクローン桜が、日本全国の桜の8割を占めるまでになったのです。
ちなみに、日本には自生種の桜は9種類※しかありませんが、これらの交配から生まれた園芸品種(栽培の桜)は、登録されているもので300種~400種、地域固有のものなど、品種として登録されていないものを含めるとその倍以上になると言われています。
※wikipediaの「サクラ」にある、野生種、自生種だけで100種程度のサクラが存在し…は完全な誤まりです。
それを考えると、たった1つの園芸品種が、日本全国を覆っている姿はある意味異様な光景であるといえるでしょう。
ということで、まずはソメイヨシノの起源から、全国に普及するまでについて駆け足で解説してみました。
ソメイヨシノについて書き始めると、開花期まで延々と続きそうなので、第1回目はこれくらいにしておきます。
今年の花見の席で、今回の話しをみんなの前ですれば、少し株が上がるかもしれません^^;
現在関東でも満開を迎えている「河津桜」や、「三春の滝ザクラ」に代表される「しだれ桜」、関東ではGWあたりに満開を迎える「八重桜」など、ソメイヨシノ以外の話題も時おり伝わっては来ますが、それらはあくまで「サブステージ」のはなし。
また、そうした桜が果たしてどういった品種で、どういう特徴を備えたものなのかわかっている人もほとんどいません。
「桜とくれば花見の宴会だ」という、大多数の日本人にとって、正直桜の品種などどうでも良いのかもしれません。
春の訪れを告げる、ソメイヨシノのあの圧倒的な群桜の華やかさを目にすれば、誰だって気分が高揚して、宴席のひとつも催したくなるものです。
自生のヤマザクラの魅力を伝えたい…
と思いながら、実のところ日本人の抱く桜のイメージが、ソメイヨシノの群桜として定着してしまった現代において、それはたぶん無理だろうなという諦めもあり、昨日の記事となりました。
ごく一部の専門家やマニアと言われるような人間でなければ、興味を持たれることもないでしょう。
なにせ、ソメイヨシノすらよく知らないという人がほとんどなのですから…^^;
そこで、今となってはマニアックなヤマザクラの話しはひとまず置いといて、現代の日本人にとっての桜=ソメイヨシノについて、しばし解説してみようと思います。
ソメイヨシノという桜を知ることで、他の桜にも、もしかしたら自生種の桜にも関心をもっていただけることを期待して…

ソメイヨシノの起源については諸説ありますが、最も有力な説は、江戸末期に江戸染井村(現在の豊島区駒込)の植木職人が、園芸品種として作出したというものです。

染井之植木屋(絵本江戸桜) 北尾政美画 1803(享和3)年
日本に9種類ある自生種(野生の桜)の中の、「江戸彼岸(エドヒガン)」という桜と「大島桜(オオシマザクラ)」という桜の交配によってできた桜ですが、江戸彼岸の特徴である「葉より先に花が咲く」ところ、大島桜の「花が大きい」ところを受け継ぎ、更に花付きが非常に良い(1つの枝に付く花の数が多い)と、見事な優性遺伝で生まれた桜です。
当初は、日本一の桜の名所として有名な「吉野山」の名前を冠した「吉野桜」として売り出されました。
「東京にいながら吉野の桜が見られる」という触れ込みで売り出したわけです。
この売り方が大ヒットとなり、「吉野桜」はまたたくまに江戸の街を覆っていきます。
江戸の三代桜の名所として知られた、上野、飛鳥山、向島は、いずれもヤマザクラを取り寄せて植えられたものでしたが、明治になると「吉野桜」に侵略されていきます。

「江戸名所百景」上野清水堂不忍ノ池 (この頃はまだヤマザクラがほとんど)
しかし、上野精養軒前の「吉野桜」の並木が、吉野山のヤマザクラと違う品種だと気づいた役人がいて、混乱を避けるためにその後(明治33年)「吉野桜」は「染井吉野」へと改名され、日本園芸雑誌に発表されます。

なぜか今も売られている「吉野桜」…たぶん大島桜系のもの(2008年靖国神社にて)

あまり知られていませんが、ソメイヨシノが爆発的に普及した背景に、この時期(明治初頭)の桜の伐採があります。
江戸末期には、大名屋敷や寺社などにヤマザクラをはじめとする多様な品種の桜が植えられていました。
しかし、明治維新となり、大名屋敷が荒廃すると、その庭に植えられていた桜や、廃仏毀釈のあおりを受けて、寺社に植えられていた桜が次々に伐られていきます。
その後、そうした場所に代わりに植えられていくのは、もちろん数百本から千本単位のソメイヨシノでした。
見た目の華やかさもありますが、ソメイヨシノはクローンということもあってか、他の桜に比べて非常に成長が早いという特徴もあります。
また、土質を選ばないという管理のしやすさもあって、出来るだけ早く見事な花が見たいという人々にとって、これほど便利な桜はなかったわけです。

更にソメイヨシノの普及に拍車を掛けたのは、近代化を急ぐ日本にとって欠かせない軍隊の拡充でした。
全国各地に配置された連隊の敷地には、決まってソメイヨシノが植えられました。
散り際の潔さから「軍国の花」として、これを積極的に利用したのです。

靖国神社「遊就館」
『同期の桜』をはじめ、桜が使われた軍歌も多くみられるように、ソメイヨシノは国家と運命を共にする精神の象徴となっていきました。
そして、戦に勝つ度に「戦勝記念」としてまた植えられていくのです。

靖国神社には戦友会の植えた桜が多数見られる
第二次世界大戦の終戦から今年で69年を迎えようとしていますが、各地の駐屯地にソメイヨシノの古木が多く見られ、いずれも花見の名所となっているのには、こうした背景があったのです。

その後の日本は戦後の高度経済成長時代を迎えますが、好景気に沸く日本の「花見」は飲めや歌えの宴会が主流となっていきます。

靖国神社の花見風景…靖国の桜の謂われを知る人は少ないでしょう
こうした花見の名所づくりに、こぞってソメイヨシノが植えられたのは言うまでもありません。
明治~大正~昭和という激動の時代、特に高度経済成長時代の日本を象徴する桜は、ソメイヨシノ以外に考えられなかったでしょう。
こうして、たった1本の木から作られたクローン桜が、日本全国の桜の8割を占めるまでになったのです。
ちなみに、日本には自生種の桜は9種類※しかありませんが、これらの交配から生まれた園芸品種(栽培の桜)は、登録されているもので300種~400種、地域固有のものなど、品種として登録されていないものを含めるとその倍以上になると言われています。
※wikipediaの「サクラ」にある、野生種、自生種だけで100種程度のサクラが存在し…は完全な誤まりです。
それを考えると、たった1つの園芸品種が、日本全国を覆っている姿はある意味異様な光景であるといえるでしょう。
ということで、まずはソメイヨシノの起源から、全国に普及するまでについて駆け足で解説してみました。
ソメイヨシノについて書き始めると、開花期まで延々と続きそうなので、第1回目はこれくらいにしておきます。
今年の花見の席で、今回の話しをみんなの前ですれば、少し株が上がるかもしれません^^;
Posted by ug at 02:42│Comments(0)│サクラぐるひ
コメントフォーム