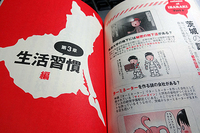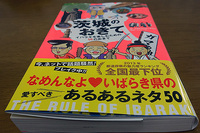2014年05月04日
5年に一度の奇祭…北茨城市の御船祭りに行ってきました

国選択無形民族文化財に指定されている「常陸大津の御船祭り(おふねまつり)」に行ってまいりました。
茨城県北茨城市で5年に一度開催されるお祭りで、東日本大震災後は初めての開催となるものです。
東日本大震災とわざわざ書いたのは、開催地である大津港は、県内で一番津波被害のひどかった地域だからです。

いまだ復興途上の大津港
津波によって、祭りに使う神船を展示していた漁業歴史資料館「よー・そろー」や隣接の市場食堂なども大きな被害を受けましたが、幸いにも船は波に乗って倒れなかったため、大きな損傷はなかったそうです。
そんな、いまだ復興途上である北茨城市では、御船祭りの開催を危ぶむ声も聞かれたようですが、「祭りで町が活気づけば…」との思いで開催にこぎ着けたとのこと。

さて、この御船祭ですが、約300年前から続く、漁港近くの佐波波地祇(さわわちぎ)神社の例大祭で、もともとは「佐波波地祇神社御祭り」と呼ばれていた(昭和59 年より常陸大津の御船祭)そうです。
神船と呼ばれる船に神輿を乗せて、水主(歌子)の歌う御船歌や囃しにあわせ300人ほどの曳き手に曳かれ町中(浜通り)を練り歩くという、漁港ならではの珍しいお祭りです。

船体にはアンコウなど大津の海で採れる魚が描かれています
船体の両側に海の幸が描かれた船は、全長15メートル、幅4メートル、重さ約5トンという巨大な木造船で、これを陸上で曳き回すわけです。
全国にはいくつかこの「御船祭り」と称するお祭りがあり、船の形をした山車を曳いたりもするようですが、いずれも山車には車輪が付いています。
ここ常陸大津の船は、その大きさもさることながら、余所と違って船底に車輪がなく、ソロバンとよばれる井桁状に組んだ木枠の上を滑らせる形で曳いていくのも大きな特徴です。

「ソロバン」…井桁に組んで使います
しかも、ただ曳くだけではなくて、船の縁に20~30人の若者がとりついて左右に大きく揺らすという、非常に見ごたえのある勇壮な祭りとなっています。
私も御船祭りのことは新聞などで見て知ってはいましたが、実際のお祭りを見るのはこれが初めて。
本日は、そんな興奮冷めやらぬ「常陸大津の御船祭り」の様子を早速紹介してみたいと思います。

私が陣取ったのは、浜通りに今年から設けられた観覧席でした。
予定では14:00にここを通過するということで、たくさんの人たちが今か今かと待ち構えていましたが、待てど暮らせどやってきません。

狭い街にすごい人出です
1時間近く待って、なんとか曳き手の方たちが目の前までやってはきましたが、いまだ神船は見えてきません。

目の前まで曳き手は来ているのに船が見えないのです
どれだけ長い綱かがわかります。
更に待つこと30分、やっと神船の先端が、角を曲がった向こう側の通りに見えてきました。

やっと見えてきました
しかし、先に述べた「ソロバン」は、一回に20m~30mほどしか敷設しないため、20mほど進んでは敷設作業、更に20mほど進んではまた敷設作業と、インターバルが結構長いのです。

先ほどの場所から20mほど一気に進みました
このインターバの時間を飽きさせないためでしょうか、ここで船の両縁に取り付いた若い衆たちが息を合わせて、船を右に左にと大きく揺すっています。
しかし、よくよく見てみると、この船を揺らす行為は、パフォーマンスというよりも、角を曲がる際や、スタートの時など、船を動かすのに勢いをつける大切な役割を持っているのだということに気づきました。
船体を揺さぶりながら方向転換中
2、3回の細かい旋回作業のあと、一気に船が向きを変えると、会場からは大きな拍手と歓声が沸き起こります。
ちなみに、こうした角を曲がる時には綱を引いた力を伝えるために、滑車とワイヤーが使われるのですが、前回平成21年のお祭りの際には、ここでワイヤーが切れて、切れたワイヤーと滑車が参加者や観客に当たり、10名の重軽傷者を出してしまいました。
そのため、今年はワイヤーの太さを3倍にして安全を図ったそうです。
船体を揺すりながら旋回が完了する様子
神船が間近にやってくる間に、約300人ほどの曳き手の方たちを観察してみましたが、いくつもの会があり、それぞれお揃いのダボに股引、腰に編んだ紐や縄を巻くというスタイルが一般的のようです。
40~50人も乗った5トンもの車輪のない船を引っ張るのですから、相当な気合いが必要でしょう。

角を曲がるのに15分ほど掛かったでしょうか、丁字路をやっと旋回し終えると、浜通りのメインストリートを一気に(といってもやはり20mほどですが^^;)曳かれてきました。
ソロバンが摩擦で焦げるせいでしょう、船体の後ろからは動くたびに白煙が上がっています。

敷設作業のために担がれたソロバンを見ると、焦げた黒い跡が残っています。
船体を揺らすときにもバキバキと音がしているので、たぶん壊れてしまうものが多いのでしょう、通りのあちこちには補充用と見られるソロバンが置かれていました。

通りのあちこちに用意されていました
目の前までやってきたところで、水主(歌子)と呼ばれる方たちでしょう、お船歌が歌われます。

その後、お囃子が始まると、ここで激しく船が左右に揺らされました。

この体勢から…

こんなになっちゃうほど揺らすのです。

船に積まれた立派な神輿も揺れてます。

船の下に敷かれたソロバンもバキバキ音を立てています^^;

サービスで(?)、10分近く揺すってくれた後、また一気に先へと進んでいきました。
その後、浜通りの東まで行くと、神事の後、神輿を船から降ろしてこれを神社に還し(還御)終了となるようですが、予定よりも大幅に時間が遅れてしまったため、私はここで現地を後にすることにしました。
というわけで、5年に一度しか見られない「常陸大津の御船祭り」の報告をさせていただきましたが、やはり実際に見ると迫力がありました。
「真壁祇園祭典」の山車の曳き回しも、なかなか他では見られないお祭りですが、船を曳き回すなんてお祭りはなかなかないでしょう。
その船にしても、もっと小さいものかと思っていたのですが、実物は本物の船と言って良い大きさでした。
茨城県民なら、是非一度は見ておきたいお祭りだと思いますが、次回見られるのは5年後です。
まだご覧になっていない方は、是非2021年に大津港を訪れてみてください。
『常陸大津の御船祭り』
※カメラ撮影と同時並行で、手持ちのコンデジで撮った動画なのでイマイチな画像で済みません^^;
お口直しにネットで見つけた5年前の動画を掲載してみます。

いまだ復興途上の大津港
津波によって、祭りに使う神船を展示していた漁業歴史資料館「よー・そろー」や隣接の市場食堂なども大きな被害を受けましたが、幸いにも船は波に乗って倒れなかったため、大きな損傷はなかったそうです。
そんな、いまだ復興途上である北茨城市では、御船祭りの開催を危ぶむ声も聞かれたようですが、「祭りで町が活気づけば…」との思いで開催にこぎ着けたとのこと。

さて、この御船祭ですが、約300年前から続く、漁港近くの佐波波地祇(さわわちぎ)神社の例大祭で、もともとは「佐波波地祇神社御祭り」と呼ばれていた(昭和59 年より常陸大津の御船祭)そうです。
神船と呼ばれる船に神輿を乗せて、水主(歌子)の歌う御船歌や囃しにあわせ300人ほどの曳き手に曳かれ町中(浜通り)を練り歩くという、漁港ならではの珍しいお祭りです。

船体にはアンコウなど大津の海で採れる魚が描かれています
船体の両側に海の幸が描かれた船は、全長15メートル、幅4メートル、重さ約5トンという巨大な木造船で、これを陸上で曳き回すわけです。
全国にはいくつかこの「御船祭り」と称するお祭りがあり、船の形をした山車を曳いたりもするようですが、いずれも山車には車輪が付いています。
ここ常陸大津の船は、その大きさもさることながら、余所と違って船底に車輪がなく、ソロバンとよばれる井桁状に組んだ木枠の上を滑らせる形で曳いていくのも大きな特徴です。

「ソロバン」…井桁に組んで使います
しかも、ただ曳くだけではなくて、船の縁に20~30人の若者がとりついて左右に大きく揺らすという、非常に見ごたえのある勇壮な祭りとなっています。
私も御船祭りのことは新聞などで見て知ってはいましたが、実際のお祭りを見るのはこれが初めて。
本日は、そんな興奮冷めやらぬ「常陸大津の御船祭り」の様子を早速紹介してみたいと思います。

私が陣取ったのは、浜通りに今年から設けられた観覧席でした。
予定では14:00にここを通過するということで、たくさんの人たちが今か今かと待ち構えていましたが、待てど暮らせどやってきません。

狭い街にすごい人出です
1時間近く待って、なんとか曳き手の方たちが目の前までやってはきましたが、いまだ神船は見えてきません。

目の前まで曳き手は来ているのに船が見えないのです
どれだけ長い綱かがわかります。
更に待つこと30分、やっと神船の先端が、角を曲がった向こう側の通りに見えてきました。

やっと見えてきました
しかし、先に述べた「ソロバン」は、一回に20m~30mほどしか敷設しないため、20mほど進んでは敷設作業、更に20mほど進んではまた敷設作業と、インターバルが結構長いのです。

先ほどの場所から20mほど一気に進みました
このインターバの時間を飽きさせないためでしょうか、ここで船の両縁に取り付いた若い衆たちが息を合わせて、船を右に左にと大きく揺すっています。
しかし、よくよく見てみると、この船を揺らす行為は、パフォーマンスというよりも、角を曲がる際や、スタートの時など、船を動かすのに勢いをつける大切な役割を持っているのだということに気づきました。
船体を揺さぶりながら方向転換中
2、3回の細かい旋回作業のあと、一気に船が向きを変えると、会場からは大きな拍手と歓声が沸き起こります。
ちなみに、こうした角を曲がる時には綱を引いた力を伝えるために、滑車とワイヤーが使われるのですが、前回平成21年のお祭りの際には、ここでワイヤーが切れて、切れたワイヤーと滑車が参加者や観客に当たり、10名の重軽傷者を出してしまいました。
そのため、今年はワイヤーの太さを3倍にして安全を図ったそうです。
船体を揺すりながら旋回が完了する様子
神船が間近にやってくる間に、約300人ほどの曳き手の方たちを観察してみましたが、いくつもの会があり、それぞれお揃いのダボに股引、腰に編んだ紐や縄を巻くというスタイルが一般的のようです。
40~50人も乗った5トンもの車輪のない船を引っ張るのですから、相当な気合いが必要でしょう。

角を曲がるのに15分ほど掛かったでしょうか、丁字路をやっと旋回し終えると、浜通りのメインストリートを一気に(といってもやはり20mほどですが^^;)曳かれてきました。
ソロバンが摩擦で焦げるせいでしょう、船体の後ろからは動くたびに白煙が上がっています。

敷設作業のために担がれたソロバンを見ると、焦げた黒い跡が残っています。
船体を揺らすときにもバキバキと音がしているので、たぶん壊れてしまうものが多いのでしょう、通りのあちこちには補充用と見られるソロバンが置かれていました。

通りのあちこちに用意されていました
目の前までやってきたところで、水主(歌子)と呼ばれる方たちでしょう、お船歌が歌われます。

その後、お囃子が始まると、ここで激しく船が左右に揺らされました。

この体勢から…

こんなになっちゃうほど揺らすのです。

船に積まれた立派な神輿も揺れてます。

船の下に敷かれたソロバンもバキバキ音を立てています^^;

サービスで(?)、10分近く揺すってくれた後、また一気に先へと進んでいきました。
その後、浜通りの東まで行くと、神事の後、神輿を船から降ろしてこれを神社に還し(還御)終了となるようですが、予定よりも大幅に時間が遅れてしまったため、私はここで現地を後にすることにしました。
というわけで、5年に一度しか見られない「常陸大津の御船祭り」の報告をさせていただきましたが、やはり実際に見ると迫力がありました。
「真壁祇園祭典」の山車の曳き回しも、なかなか他では見られないお祭りですが、船を曳き回すなんてお祭りはなかなかないでしょう。
その船にしても、もっと小さいものかと思っていたのですが、実物は本物の船と言って良い大きさでした。
茨城県民なら、是非一度は見ておきたいお祭りだと思いますが、次回見られるのは5年後です。
まだご覧になっていない方は、是非2021年に大津港を訪れてみてください。
『常陸大津の御船祭り』
※カメラ撮影と同時並行で、手持ちのコンデジで撮った動画なのでイマイチな画像で済みません^^;
お口直しにネットで見つけた5年前の動画を掲載してみます。
Posted by ug at 02:55│Comments(1)│ちいき
この記事へのコメント
おふなまつりです
Posted by 地元民 at 2017年04月28日 18:23
コメントフォーム