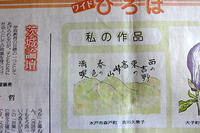2013年05月21日
サクラの寿命

たぶん公園周辺で一番古い山桜(樹齢100年超?)
先日の『「弘前桜まつり」リポート(桜編)』でも触れましたように、弘前公園の桜を管理している樹木医の小林勝氏は「桜には寿命がない」と話されていますが、果たして“一般的に”桜の寿命はどれくらいと言われているかご存知ですか?
そもそも桜の寿命が話題になったのは、21世紀を迎えようとする1990年代後半でした。
第二次世界大戦後に植えられた全国各地のソメイヨシノの衰弱が目立つようになり、「ソメイヨシノ60年寿命説」がまことしやかに囁かれ始めたのです。
桜関連の書籍にも「早すぎる成長、早すぎる死」と言った言葉が並び、もはやそれは定説とさえ言えるようになっていました。
果たして、本当にソメイヨシノの寿命は60年なのか…
そんな疑問に対して明快な回答をしてくれているのが、日本花の会の主任研究員である和田博幸氏です。
和田さんは、1000本を超えるソメイヨシノを調査し、樹齢と危険度との関係を考察したそうです。
その結果によると、やはり加齢とともに危険度が増すことが分かったそうで、特に樹齢40年を超えると衰弱するものが極端に増え、さらに年を重ねる毎に危険度の高いものが増えていったとのこと。
な~んだ、やっぱり60年が寿命じゃないか…と思われるのはまだ早い。
実はこれ、単純に年をとったから弱ったというものでもなく、生育環境による影響が大きいのだそうです。
観測したソメイヨシノは10mほどの間隔で植えられているものでしたが、ソメイヨシノは巨大化しやすく、また枝葉の密生も激しいので、30年もすると隣り合ったものと枝が重なり合ってしまいます。

市内にある30年を迎えようとしているソメイヨシノの並木
ここで、ソメイヨシノならではのおもしろい現象が起こるのですが、クローンであるソメイヨシノは、双方から伸びた枝を自分自身であると認識し合い、隣の枝も抵抗なく自分の樹冠の中に受け入れてしまうのです。
上部では光を求めて上へ上へと伸びる反面、重なり合った枝は日照不足になり、40年頃には徐々に冬枯れを起こし始めるのだとか。
そこにもってきて、40年ともなると間違いなく桜の名所となり、たくさんの人が訪れるようになるので、根元を踏みつけるようになったり、人が歩きやすいように太枝を剪定したり、歩道整備などが行われるようになってきます。
こうしていっそう樹勢が衰退し、腐朽菌の侵入を許すことになり枯死するものが多くなると言うわけです。
とまぁ、非常にわかりやすく解説してくれているのですが、要は人が作った桜は、手を掛けてあげないと弱りやすいということなのです。
では自然の桜はどうかというと、これも生育環境に大きく左右されるのは変わりませんが、一般的には山桜で200~300年、桜の中でも一番長生きすると言われる江戸彼岸で500年以上と言われています。
山桜にも、なかには樹齢500年を超えるものもあるし、江戸彼岸に至っては日本で一番古いと言われる「山高神代桜」のように樹齢1800年以上というオバケのような桜まであります。

日本で一番古いと言われる「山高神代桜」(エドヒガン)
三春の滝桜もそうですが、大体1000年近くも長生きする桜はほぼ江戸彼岸と言って良いでしょう。
残念ながら、当地には「名勝」指定時のような、山桜の古木や巨木はなくなってしまいましたが、参道沿いに辛うじて2本、100年を超えるだろう山桜が残っています。
しかしこれも生育環境が良いとはとても言えず、我らが調査にあたった時には既にサルノコシカケのようなキノコが生え、瀕死の状態となっていました。
長生きさせるばかりが良いとは思いませんが、出来れば寿命を全うできるような生育環境は整えてあげたいもの。
ソメイヨシノばかりでなく、里にある桜は人が手をかけてあげなければ短命に終わってしまいます。
磯部桜川公園にある山桜も、孫どころか、曾孫、玄孫の代にまで見事な姿を見せてくれるように、これから生育環境の改善に励んでいきたいと思っています。
桜関連の書籍にも「早すぎる成長、早すぎる死」と言った言葉が並び、もはやそれは定説とさえ言えるようになっていました。
果たして、本当にソメイヨシノの寿命は60年なのか…
そんな疑問に対して明快な回答をしてくれているのが、日本花の会の主任研究員である和田博幸氏です。
和田さんは、1000本を超えるソメイヨシノを調査し、樹齢と危険度との関係を考察したそうです。
その結果によると、やはり加齢とともに危険度が増すことが分かったそうで、特に樹齢40年を超えると衰弱するものが極端に増え、さらに年を重ねる毎に危険度の高いものが増えていったとのこと。
な~んだ、やっぱり60年が寿命じゃないか…と思われるのはまだ早い。
実はこれ、単純に年をとったから弱ったというものでもなく、生育環境による影響が大きいのだそうです。
観測したソメイヨシノは10mほどの間隔で植えられているものでしたが、ソメイヨシノは巨大化しやすく、また枝葉の密生も激しいので、30年もすると隣り合ったものと枝が重なり合ってしまいます。

市内にある30年を迎えようとしているソメイヨシノの並木
ここで、ソメイヨシノならではのおもしろい現象が起こるのですが、クローンであるソメイヨシノは、双方から伸びた枝を自分自身であると認識し合い、隣の枝も抵抗なく自分の樹冠の中に受け入れてしまうのです。
上部では光を求めて上へ上へと伸びる反面、重なり合った枝は日照不足になり、40年頃には徐々に冬枯れを起こし始めるのだとか。
そこにもってきて、40年ともなると間違いなく桜の名所となり、たくさんの人が訪れるようになるので、根元を踏みつけるようになったり、人が歩きやすいように太枝を剪定したり、歩道整備などが行われるようになってきます。
こうしていっそう樹勢が衰退し、腐朽菌の侵入を許すことになり枯死するものが多くなると言うわけです。
とまぁ、非常にわかりやすく解説してくれているのですが、要は人が作った桜は、手を掛けてあげないと弱りやすいということなのです。
では自然の桜はどうかというと、これも生育環境に大きく左右されるのは変わりませんが、一般的には山桜で200~300年、桜の中でも一番長生きすると言われる江戸彼岸で500年以上と言われています。
山桜にも、なかには樹齢500年を超えるものもあるし、江戸彼岸に至っては日本で一番古いと言われる「山高神代桜」のように樹齢1800年以上というオバケのような桜まであります。

日本で一番古いと言われる「山高神代桜」(エドヒガン)
三春の滝桜もそうですが、大体1000年近くも長生きする桜はほぼ江戸彼岸と言って良いでしょう。
残念ながら、当地には「名勝」指定時のような、山桜の古木や巨木はなくなってしまいましたが、参道沿いに辛うじて2本、100年を超えるだろう山桜が残っています。
しかしこれも生育環境が良いとはとても言えず、我らが調査にあたった時には既にサルノコシカケのようなキノコが生え、瀕死の状態となっていました。
長生きさせるばかりが良いとは思いませんが、出来れば寿命を全うできるような生育環境は整えてあげたいもの。
ソメイヨシノばかりでなく、里にある桜は人が手をかけてあげなければ短命に終わってしまいます。
磯部桜川公園にある山桜も、孫どころか、曾孫、玄孫の代にまで見事な姿を見せてくれるように、これから生育環境の改善に励んでいきたいと思っています。
Posted by ug at 09:00│Comments(1)│サクラぐるひ
この記事へのコメント
立木(桜)の樹齢を知る方法は?
Posted by 相馬利彦 at 2018年07月30日 05:52
コメントフォーム