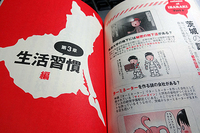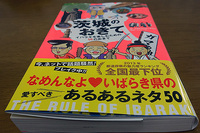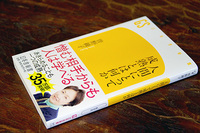2014年03月03日
デキる男がやっている「やる気の出る脳の使い方」

みなさん、毎日の生活パターンが脳の「やる気」と密接な関係にあることをご存知ですか?
まずは、次に挙げる日常の行動に自分がいくつ該当するか確認してみてください。
◇ 起床時間が一定でない
◇ 朝食をとらない
◇ オフィスに着いてすぐ重要な仕事に取りかかる
◇ 時間を決めず、出来る限り多くの仕事を片付ける
◇ 朝、昼は軽めで、夜に一番豪華な食事をする
◇ 大事な仕事は、午後からに回す
◇ 一日の仕事の出来で気分が浮き沈みする
◇ 仕事は家に持ち帰ってもやる
◇ 寝る前まで集中して勉強をしている
◇ 休日は家でゴロゴロしていることが多い
実はこうした生活習慣が、脳のパフォーマンスを落としているかもしれないのです。
頑張ろうと思っても、脳のパフォーマンスが低ければ、やる気も起きないし、良い結果も出ません。
逆に脳のパフォーマンスの高い時には、自然にやる気も湧いてくるし、仕事も効率的にこなすことが出来るものです。
しかし、いつもいつも脳が高いパフォーマンスを保っていられるかというと、残念ながら生体リズムがそれを許してはくれません。

ブルーの線が脳のサーカディアンリズム
これから紹介するのは、サーカディアンリズム(概日リズム)と呼ばれる、約24時間周期で変動する動物や生物の生理現象を利用した、脳の「やる気」アップ法です。
サーカディアンリズムに乗った上手な脳の使い方を知って、最高のパフォーマンスを発揮できる生活習慣を身につけませんか。

◆毎日決まった時間に起きる
毎朝決まった時間に起きるというのは、脳にとって一番重要です。
人間の細胞に備わっている体内時計を毎日リセットしていると、いつも時差ボケのような状態になってしまいます。
また、スタート時間がずれると脳の覚醒度や生活時間もずれるので、脳をフル回転させる適切なタイミングを失ってしまいます。
◆起きたら太陽の光を浴びる
人は情報の8割を視覚で受け取っていますが、太陽はこの中でももっとも強力で、脳全体が朝だということを認識します。
人間の体内時計は地球の自転よりやや長くプログラムされているため、その誤差をリセットする必要があり、視覚から入る光の情報がこの役目を果たしているのです。
◆何も考えないで行えるルーティンを決める
毎朝散歩に出て、同じ人に挨拶し、同じ喫茶店の同じ席に座る…というようなルーティンを持っていると脳を上手く目覚めさせることが出来ます。
逆に毎朝違う行動をとると、思考系の脳(大脳新皮質)を使ってしまうことになり、徐々に覚醒していく脳を上手く使えません。
何も考えずにサクサク動くことで、脳は深部から徐々に目覚めてくるのです。
◆食事でカラダを覚醒させる
太陽の光を浴びることで脳が朝だと認識したように、カラダは食事をすることでこれを認識します。
カラダも食事をとることで、徐々に目覚めていくので、朝から効率的に仕事をこなしたい人は必ず朝食をとりましょう。
◆新聞を声を出して読む
視覚から入る文字情報よりも、声に出して耳から入力した方が情報をより理解することができます。
また、話す練習にもなったり、日中目や耳から入ってくる情報を処理しやすくなります。
音読という作業は脳をフル回転させるための準備運動と考えましょう。

◆オフィスに着いたらデスクの片付けなど簡単な作業を
脳がまだ十分回転していない状態で、いきなり重要な仕事に向かうのは効率が良くありません。
簡単な作業をひとつずつクリアすることで、脳内物質(ドーパミン)が出て達成感を感じます。
このプチ達成感はやる気を起こすきっかけのひとつ。
重要な案件は単純な作業の後に取りかかるようにしましょう。
◆50分仕事をしたら10分間の休憩を
仕事をクリアすることで(ドーパミンが出て)達成感を味わうと、次々に仕事をこなしていきたくなりますが、自分が思っている以上に緊張感を持続するのは困難です。
脳がフル回転していられるのはせいぜい2時間。
バーンアウトしないためにも、ある程度(3つか4つ)の仕事をこなしたら、脳を休ませましょう。
10分程度の休憩なら脳の回転速度は落ちません。
休憩時に椅子から立ち上がって脚を動かせば、血流が促され「脳のストレッチ」にもなります。
◆仕事に締め切りを設ける
時間を決めずにダラダラ仕事をするというのは、脳の回転数が上がらない一番非効率な仕事の仕方。
自分で仕事に締め切りを設け、脳に緊張感や刺激を与えて、ここぞというときに脳の回転数が上がるようにしましょう。
◆食事は一点ランチ豪華主義で
脳の機能を高く保つためには、朝食と昼食をしっかりとり、夜は控えめというのが基本。
その日一番食べたいものをランチで食べるというのがオススメ。
◆重要な仕事は「昼メシ前」に済ませる
↑のグラフをご覧いただければわかるように、脳の覚醒度は昼前に一度目のピークを迎えます。
その後やや下降して夕方以降に再び上昇します。
この2つのピークを上手く使い、1回目のピークをその日の中で一番重要な仕事に充てると効果的です。
気の重い案件は早めに済ませてしまうことで、その後の時間が有効に活用できるようになります。

◆仕事を家に持ち帰らない
「昼」でも書いたように、脳は時間の制約がないと、ここぞという時に回転が上がらなくなります。
仕事を家に持ち帰るというのも同様の行為。
仕事に時間の制約を設け、絶対に家には持ち帰らないというのがデキる男。
◆「入眠儀式」でスムーズな入眠を
寝る前の行動をパターン化しておくと、脳とカラダが眠りの準備に入りやすくなります。
起きてからのルーティンのように、何も考えずに手順を踏みむことで自然に眠くなっていくのです。
また、睡眠時間も脳のメンテナンスのためには、最低6時間は必要です。
毎日の起床時間に合わせて、就寝時間も決まった時間に設定するのがベスト。
◆眠る前にぼんやりと勉強する
睡眠にはレム睡眠とノンレム睡眠がありますが、カラダが眠って脳が動いているレム睡眠状態のときには、脳は特に寝る直前の情報を覚えています。
レム睡眠中はコンピューターの再起動のように、要らない情報が消され、濃い情報だけが残って整理されるので、寝る直前にぼんやりと本を眺める程度の勉強法が有効なのです。

◆仕事から離れる
仕事以外のコミュニティに参加したり、自分だけのスペースを作って寛いだりすることは、脳のリフレッシュになります。
また、楽器の演奏や、ガーデニングといった手を動かす趣味も、脳に刺激を与え、血流を促すため、こちらも脳のリフレッシュにはとても有効です。
こうした仕事以外の人間関係などで、ちょっとした幸福感を感じるとき、脳内物質(セロトニン)が分泌され、これが脳を癒やし、良い状態に安定させてくれるのです。
また、仕事につながるIT機器もシャットアウトすれば、脳のリラックス度は飛躍的にアップするはずです。
というわけで、やや偉そうに書いてしまいましたが、これ、『一生衰えない脳のつくり方・使い方~成長する脳のマネジメント術』の著者である脳神経外科医で医学博士築山節氏による、雑誌『Tarzan』掲載記事を簡単にまとめてみたものです。
記事は『「やる気スイッチ」の入れ方には手順があった』というものですが、内容的にはアラフォー世代向けのものとなっており、『一生衰えない…』からの抜粋のようでした。
30代前半位までは、生活リズムが乱れても、体力もあり多少の無理は利きますが、アラフォー世代となるとそうもいかなくなってくるようです。
しかしながら、総合力がついて脳が新の実力を発揮できるのは40歳を過ぎてからとも言います。
正直なところ、最初の設問のほとんどに合致してしまった私ですが、今後は自分の体力のことも考えて、少しずつ生活習慣を見直してみようと思います。
Posted by ug at 01:16│Comments(0)│ほんのはなし
コメントフォーム