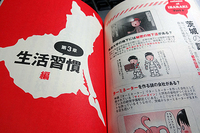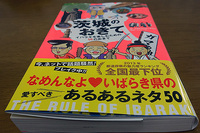2013年10月06日
『ネットのバカ』…99.9%はクリックする奴隷
なかなか刺激的なタイトルと帯の見出しに惹かれて買ってしまい、昨夜ブログも書かず一気読みしました。
元博報堂社員でネットニュース編集者・PRプランナーの中川淳一郎氏が書いた前作『ウェブはバカと暇人のもの』の続編です。
『ウェブは…』は2009年刊行の著書で、当時ブックオフにも何冊も並んでいたのですが、とうとう買わず仕舞いでした。
しかし、今回はちょうど『ローマ人の物語』に疲れたところだったので、“やわらかい”ものを…という気分にピッタリ、私には珍しく今年7月発刊のまさしく“新書”に手が伸びたというわけです。
そんな“刺激的な”帯の見出しは次の通りです。
まぁ、とにかく日本のネット事情に詳しい方でして、本格的にネットが普及し始めた2000年代前半辺りからの変遷を紹介しているわけですが、本書では主に前著『ウェブはバカと…』(2009年発刊)以降の4年間について書いています。
“ネット中毒”と自分でも認めている著者ですが、得てしてこの手の本は、ユーザーサイドの目線による、ネット事情の紹介だけで終わってしまうものです。
しかし、本書の良いところは、ネット中毒者でありながら醒めた目で、今のネット社会を俯瞰しているところ。
私もダイヤル回線の頃からのネットユーザーでして、一時は間違いなく“中毒者”でしたから、凄く共感する部分の多い本でした。
とはいえ、著者のような情報通ではもちろんないので、ネット上で起こった様々な事件(?)など、昔懐かしのものもあるものの、ほとんどは「へー」と、そのバカさ加減に感心しながら、面白おかしく読ませていただきました。
そんな本書について、いつものように私の読書メモ代わりに紹介してみたいと思うのですが、要約の苦手な私のこと、ついつい長文になってしまうので、2回に分けて書いてみることにします。
まず、本日は序章、終章含めて全10章のうち、サブタイトルの「99.9%はクリックする奴隷」について書かれた序章~第3章までをご紹介。
◆序章 「ネットが当たり前になった時代に」
 まず、この4年で大きく変わったのは、もはやネットは「ごく当たり前のもの」という時代になったこと。
まず、この4年で大きく変わったのは、もはやネットは「ごく当たり前のもの」という時代になったこと。
ネットが一般的なインフラになり、これなしでは仕事も生活も成り立たなくなりつつあるということです。
ただ、時代が変わっても、そのツールが古臭くなったら、発言に責任を持たぬまま、さっさと次のツールに熱狂する、という光景は変わらないと言います。
ネット上ではこれまでも、様々ないざこざが起こってきましたが、ネットが当たり前になり「人口」が増えれば、さらなるカオスを招くことは間違いないだろうと。
そこで、「当たり前になったインターネットで私たちがどう生きていくか」を考えるにあたって、知っておくべき2つの真実を挙げています。
①勝ち組は少数派
②勝者が総取り
これを著者は、ネットの世界に限らず人間の有史以来変わらない「定理」だと言っています。
これらを無視したままネットの世界を信じていると、搾取され続けるどころか、誰かが唱えた「一発逆転」を狙って人生崩壊、あるいは金銭的被害を受けないとも限らないと警告します。
そんな著者は、次の4つの姿勢に基づき、この4年間のネットでの事象について論じていきます。
◆第1章 「ネットの言論は不自由なものである」
「ネットほど発言に不自由なものはない」
雑誌では通じる発言も、ネットでは過剰な反応から炎上したり、「正論」の盲点を突くような発言は許してもらえない。
また、SNSの普及により、ブログ界以上にネットリテラシーの低い層が増え、バカらしい事象が次々と起こるようになってしまった。
ツイッターは「バカ発見器」とまで呼ばれるようになった、と。

今夏話題になった「悪ふざけ投稿」
「立教大生レイプ擁護事件」や、帯にもあった「来店した有名人情報をリークする店員」他、様々なネットでの騒動を挙げています。
これは一般人だけの話ではなく、ちょっとした発言で叩かれ、ツイッターをやめることになった芸能人を何人も紹介しています。
ただ、逆に芸能人の場合、トラブルめいた事態に陥っても、対応さえ間違わなければ、膨大なフォロワーに擁護されて、事を優位に運べるという事例もいくつか紹介しています。
これをもって、「フォロワー数は戦闘力」であると言い、あくまで現実世界での知名度、影響力がそのままネットでも反映されてしまうのだと言っています。

260万以上のフォロワーを持つ有吉弘行のtwitter
そんなネットでの「階級社会」は、現実世界より厳しいとも言っています。
ネットで一般人が「成り上がる」のは、「可能性は低いがゼロではないという程度」だそうです。
一般の人たちの消費は、そのままごく一部の勝者のカネになっていて、ネットとはカネが渦巻く世界なのだ、と。
◆第2章 「99.9%はクリックし続ける奴隷」
ネット上のツール、例えばSNSの世界では、最初は一部のマニアや先進的な人が飛びつき、一時的に有名になったりするものの、結局は「有名人」や「芸能人」がそこに参入してきて、場を支配してしまいます。
基本的にネットの世界ではこのストーリーが繰り返されているわけです。
2004年頃からブログが爆発的に普及し始めると同時に、「アルファ・ブロガー」(トップクラスの人気ブロガー)なる言葉が生まれ、企業のプロモーションの企画書には、必ずアルファブロガーのリストが列挙されました。
この頃までは、インターネットは完全に「個人」のものでした。
しかし、企業が見た目の良いコンテンツ(リッチコンテンツ)づくりに血眼になっているのを尻目に、楽天等のネット販売サイトがひたすら「ワケあり明太子、95%オフ!」と扇情的な言葉を並べ、デザインもへったくれもないようなバナー広告を大量に投下し続けました。
どちらの手法が有効だったかは、言わずもがなでしょう。
ネット広告と時を同じくして、ブログの世界ではアメブロが参入、“ブログの女王”ココログの眞鍋かをりや、ヤプログの中川翔子の人気に目をつけ、芸能人を囲い込んでPVを稼ぎ出します。

現在はlivedoorでブログを書く“ブログの女王”眞鍋かをり
芸能人の影響力は凄まじく、先のアルファブロガーのPV(ページビュー)をあっさり超えてしまうわけです。
芸能人も戦略的にブログを利用するようになるわけですが、その後これが企業のプロモーションと結びついた「ステルスマーケティング」※を生み出します。
※広告であることを隠して宣伝すること
ステルスマーケティング(ステマ)は、ブログからツイッターの時代になっても行われていますが、Sランクの芸能人ブロガーだと、記事1本で200万円、2本で300万円もらえるそうです。
ブログにしろツイッターにしろ、忙しい中芸能人がそれに手を染めるのは、突き詰めれば「カネ」と言うことです。

ステマがバレて派手に報じられたほしのあき
しかし、有名なペニーオークション事件等、ステマが暴かれた芸能人も多数出ています。
それにしても、こうした有名人の言葉を信用してしまう「カモ」は、ヤフー調査で4割にも上るそう。
賢明な人から見れば「バカじゃねーの?」と思うような話であっても、世間の4割はこの程度の認識なのだと言います。
結局、「影響力」には知名度による格差が生まれ、それは一握りの有名人がトップに君臨し、ほぼ全体を占める一般人に影響を与えるという、ピラミッド構造なのだということ。
そして、われわれ一般人の1クリック、1いいね、1RTはすべて強者をより強者にするために使われているのだと。

いわばあなたは「クリックする機械」でしかないのだとまで言います。
こうした「格差」は、現実世界よりもネットの方が極端なのです。
◆第3章 「一般人の勝者は1人だけ」
リアルの場での知名度がネットでも影響力を持つことを述べてきましたが、一般人でも何らかの分野で「時の人」となるケースもあります。
しかし、それもせいぜい1ジャンルにトップの1人か2人。
これを「1ジャンルに1人の法則」と言っています。
ですから、まだ誰も手をつけていないようなジャンルを見つけて、そこで第一人者となれば、注目される可能性は高いでしょう。
ただし、注目を浴び続けるのはなかなか困難です。
こうした1ジャンルで有名になった人の例も何人か挙げられています。
ところで、人はなぜPV稼ぎと拡散を求めるのか…
儲かるか、あるいは人気者になり、自己承認欲求が満たされるからだと言います。
これに便乗してSNSで「バズる」(話題になる)ためのテクニック本や、コンサルタントを名乗る者まで出てきていますが、子どもでもバカでもツイッターをやる時代になっては、ネットへの過大な幻想はもはや捨てなければならないと指摘します。
とまぁ、本日も結局テキストだらけの長文になってしまいました^^;
全文読んでくれる方はまずいないと思いますが、やはり興味のある分野はあれもこれも書きたくなってしまって…
ちなみに、現在の私はSNSにはほとんど手を出していないし、書店にない本をamazonで買ったり、記事を書く時にバックボーンを調べたりするくらいで、余計なサイトは訪れなくなりました。
このブログが精一杯で、そんな時間もないからですが、つぶやく暇もないほどリアルを忙しくするのが一番の対処法かもしれません^^;

しかし、今回はちょうど『ローマ人の物語』に疲れたところだったので、“やわらかい”ものを…という気分にピッタリ、私には珍しく今年7月発刊のまさしく“新書”に手が伸びたというわけです。
そんな“刺激的な”帯の見出しは次の通りです。
◆金目当てにステマをやる芸能人
◆課金ゲームに大金をむしられる中毒者
◆レイプ犯を擁護して大炎上した大学生
◆来店した有名人情報をリークする店員
◆陰謀論に飛びつく“愛国者”
◆ネットで一攫千金を喧伝するエヴァンジェリスト
◆ネットの論理を理解せずに不興を買う企業
…このバカだらけの海をどう泳いでいくか?
まぁ、とにかく日本のネット事情に詳しい方でして、本格的にネットが普及し始めた2000年代前半辺りからの変遷を紹介しているわけですが、本書では主に前著『ウェブはバカと…』(2009年発刊)以降の4年間について書いています。
“ネット中毒”と自分でも認めている著者ですが、得てしてこの手の本は、ユーザーサイドの目線による、ネット事情の紹介だけで終わってしまうものです。
しかし、本書の良いところは、ネット中毒者でありながら醒めた目で、今のネット社会を俯瞰しているところ。
私もダイヤル回線の頃からのネットユーザーでして、一時は間違いなく“中毒者”でしたから、凄く共感する部分の多い本でした。
とはいえ、著者のような情報通ではもちろんないので、ネット上で起こった様々な事件(?)など、昔懐かしのものもあるものの、ほとんどは「へー」と、そのバカさ加減に感心しながら、面白おかしく読ませていただきました。
そんな本書について、いつものように私の読書メモ代わりに紹介してみたいと思うのですが、要約の苦手な私のこと、ついつい長文になってしまうので、2回に分けて書いてみることにします。
まず、本日は序章、終章含めて全10章のうち、サブタイトルの「99.9%はクリックする奴隷」について書かれた序章~第3章までをご紹介。
◆序章 「ネットが当たり前になった時代に」
 まず、この4年で大きく変わったのは、もはやネットは「ごく当たり前のもの」という時代になったこと。
まず、この4年で大きく変わったのは、もはやネットは「ごく当たり前のもの」という時代になったこと。ネットが一般的なインフラになり、これなしでは仕事も生活も成り立たなくなりつつあるということです。
ただ、時代が変わっても、そのツールが古臭くなったら、発言に責任を持たぬまま、さっさと次のツールに熱狂する、という光景は変わらないと言います。
ネット上ではこれまでも、様々ないざこざが起こってきましたが、ネットが当たり前になり「人口」が増えれば、さらなるカオスを招くことは間違いないだろうと。
そこで、「当たり前になったインターネットで私たちがどう生きていくか」を考えるにあたって、知っておくべき2つの真実を挙げています。
①勝ち組は少数派
②勝者が総取り
これを著者は、ネットの世界に限らず人間の有史以来変わらない「定理」だと言っています。
これらを無視したままネットの世界を信じていると、搾取され続けるどころか、誰かが唱えた「一発逆転」を狙って人生崩壊、あるいは金銭的被害を受けないとも限らないと警告します。
そんな著者は、次の4つの姿勢に基づき、この4年間のネットでの事象について論じていきます。
◇ネットに関する基本4姿勢
・人間はどんなツールを使おうが、基本的能力がそれによって上がることはない。
・ツールありきではなく、何を言いたいか、何を成し遂げたいかによって人は行動すべき。ネットがそれを達成するのに役立つのであれば、積極的に活用する。
・ネットがあろうがなかろうが有能な人は有能なまま、無能な人は無能なまま。
・1人の人間の人生が好転するのは人との出会いによる。
◆第1章 「ネットの言論は不自由なものである」
「ネットほど発言に不自由なものはない」
雑誌では通じる発言も、ネットでは過剰な反応から炎上したり、「正論」の盲点を突くような発言は許してもらえない。
また、SNSの普及により、ブログ界以上にネットリテラシーの低い層が増え、バカらしい事象が次々と起こるようになってしまった。
ツイッターは「バカ発見器」とまで呼ばれるようになった、と。
今夏話題になった「悪ふざけ投稿」
「立教大生レイプ擁護事件」や、帯にもあった「来店した有名人情報をリークする店員」他、様々なネットでの騒動を挙げています。
これは一般人だけの話ではなく、ちょっとした発言で叩かれ、ツイッターをやめることになった芸能人を何人も紹介しています。
ただ、逆に芸能人の場合、トラブルめいた事態に陥っても、対応さえ間違わなければ、膨大なフォロワーに擁護されて、事を優位に運べるという事例もいくつか紹介しています。
これをもって、「フォロワー数は戦闘力」であると言い、あくまで現実世界での知名度、影響力がそのままネットでも反映されてしまうのだと言っています。
260万以上のフォロワーを持つ有吉弘行のtwitter
そんなネットでの「階級社会」は、現実世界より厳しいとも言っています。
ネットで一般人が「成り上がる」のは、「可能性は低いがゼロではないという程度」だそうです。
一般の人たちの消費は、そのままごく一部の勝者のカネになっていて、ネットとはカネが渦巻く世界なのだ、と。
◆第2章 「99.9%はクリックし続ける奴隷」
ネット上のツール、例えばSNSの世界では、最初は一部のマニアや先進的な人が飛びつき、一時的に有名になったりするものの、結局は「有名人」や「芸能人」がそこに参入してきて、場を支配してしまいます。
基本的にネットの世界ではこのストーリーが繰り返されているわけです。
2004年頃からブログが爆発的に普及し始めると同時に、「アルファ・ブロガー」(トップクラスの人気ブロガー)なる言葉が生まれ、企業のプロモーションの企画書には、必ずアルファブロガーのリストが列挙されました。
この頃までは、インターネットは完全に「個人」のものでした。
しかし、企業が見た目の良いコンテンツ(リッチコンテンツ)づくりに血眼になっているのを尻目に、楽天等のネット販売サイトがひたすら「ワケあり明太子、95%オフ!」と扇情的な言葉を並べ、デザインもへったくれもないようなバナー広告を大量に投下し続けました。
どちらの手法が有効だったかは、言わずもがなでしょう。
ネット広告と時を同じくして、ブログの世界ではアメブロが参入、“ブログの女王”ココログの眞鍋かをりや、ヤプログの中川翔子の人気に目をつけ、芸能人を囲い込んでPVを稼ぎ出します。

現在はlivedoorでブログを書く“ブログの女王”眞鍋かをり
芸能人の影響力は凄まじく、先のアルファブロガーのPV(ページビュー)をあっさり超えてしまうわけです。
芸能人も戦略的にブログを利用するようになるわけですが、その後これが企業のプロモーションと結びついた「ステルスマーケティング」※を生み出します。
※広告であることを隠して宣伝すること
ステルスマーケティング(ステマ)は、ブログからツイッターの時代になっても行われていますが、Sランクの芸能人ブロガーだと、記事1本で200万円、2本で300万円もらえるそうです。
ブログにしろツイッターにしろ、忙しい中芸能人がそれに手を染めるのは、突き詰めれば「カネ」と言うことです。
ステマがバレて派手に報じられたほしのあき
しかし、有名なペニーオークション事件等、ステマが暴かれた芸能人も多数出ています。
それにしても、こうした有名人の言葉を信用してしまう「カモ」は、ヤフー調査で4割にも上るそう。
賢明な人から見れば「バカじゃねーの?」と思うような話であっても、世間の4割はこの程度の認識なのだと言います。
結局、「影響力」には知名度による格差が生まれ、それは一握りの有名人がトップに君臨し、ほぼ全体を占める一般人に影響を与えるという、ピラミッド構造なのだということ。
そして、われわれ一般人の1クリック、1いいね、1RTはすべて強者をより強者にするために使われているのだと。

いわばあなたは「クリックする機械」でしかないのだとまで言います。
こうした「格差」は、現実世界よりもネットの方が極端なのです。
◆第3章 「一般人の勝者は1人だけ」
リアルの場での知名度がネットでも影響力を持つことを述べてきましたが、一般人でも何らかの分野で「時の人」となるケースもあります。
しかし、それもせいぜい1ジャンルにトップの1人か2人。
これを「1ジャンルに1人の法則」と言っています。
ですから、まだ誰も手をつけていないようなジャンルを見つけて、そこで第一人者となれば、注目される可能性は高いでしょう。
ただし、注目を浴び続けるのはなかなか困難です。
こうした1ジャンルで有名になった人の例も何人か挙げられています。
ところで、人はなぜPV稼ぎと拡散を求めるのか…
儲かるか、あるいは人気者になり、自己承認欲求が満たされるからだと言います。
これに便乗してSNSで「バズる」(話題になる)ためのテクニック本や、コンサルタントを名乗る者まで出てきていますが、子どもでもバカでもツイッターをやる時代になっては、ネットへの過大な幻想はもはや捨てなければならないと指摘します。
とまぁ、本日も結局テキストだらけの長文になってしまいました^^;
全文読んでくれる方はまずいないと思いますが、やはり興味のある分野はあれもこれも書きたくなってしまって…
ちなみに、現在の私はSNSにはほとんど手を出していないし、書店にない本をamazonで買ったり、記事を書く時にバックボーンを調べたりするくらいで、余計なサイトは訪れなくなりました。
このブログが精一杯で、そんな時間もないからですが、つぶやく暇もないほどリアルを忙しくするのが一番の対処法かもしれません^^;
燃やせ!! 体脂肪 「ダイエット日記」

10月5日(土)
◇ランニング:なし
◆体重 70.6kg (-0.3kg) 身長176cm
◇目標の68kgまであと2.6kg
ジョギングを4日もしていないけど、昼のカロリー制限で頑張りました。
でも、こんな微減では間に合わないぞ?^^;
Posted by ug at 23:10│Comments(0)│ほんのはなし
コメントフォーム