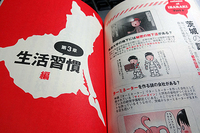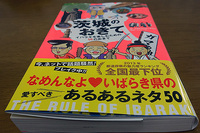2008年09月14日
『きよしこ』
自身が吃音(どもり)を持つ重松清氏が、同じ吃音
の子を持つお母さんから「励ましてあげてください」
という手紙をもらったことから“お話”は始まる。
結局重松氏はこの子に手紙を書くことはなかった
が、その代わり「個人的なお話」として、この『きよ
しこ』を書いて、少年に送ることになる。
どこまでが実体験かはわからない。
しかし、吃音を持つ少年の心を描いた、重松氏の
自叙伝的作品となっている。
主人公の少年は小さい頃から吃音を持ち、言い
たいことが言えずに育つ。
その上、父親の仕事で転校を繰り返すため、友だ
ちが出来ない。
心の中ではすらすらと喋れる言葉も、声にすると
「カ」行や「タ」行、濁音で始まる言葉が上手く言え
ず、最初の自己紹介の「キヨシ」でつまずいてしまう
のだった。
「・・・なんでも話せる友だちが欲しい」
「きよしこ」は、そんななんでも話せる、少年の空
想の中の友だちだ。
少年はクリスマスの夜にたった一度だけ出会えたこ
のきよしこから、大事なことを教わる。
「それが本当に伝えたいことだったら・・・伝わる
よ、きっと」
重松氏の得意な短編連作形式のこの“お話”は、
小・中・高校時代、部活動など、各年代で少年と
強く関わる人間関係が描かれているが、その一
話一話に少年の「本当に伝えたいこと」が散りば
められている。
最初は苛立ちや諦めが目立ち、読んでいて切な
くなったが、痛みを抱えながらも徐々に強くなって
いく少年や、少年を取り巻く人々になんとも暖かい
気持ちにさせられ、自然に涙がこぼれる。
また、少年がここぞという時に伝えようとする「思
い」のこもった言葉には感動させられた。
レビューなどには「障害のある方は是非一読を…」
みたいな言葉が見受けられるが、果たしてそう
だろうか?
健常者こそ読むべきだと自分は思う。
冒頭のお母さんが手紙に書いた「吃音なんかに
負けないで…」の“なんか”。
少年が嫌がったように、形だけの同情や憐れみ
は差別と変わらないのだと強く感じた。
もちろん、この本が言いたいのはそういうことで
はないだろうが…
さて、先の『流星ワゴン』で書いたように、この『きよ
しこ』もまた最後に救いが…現実を受け入れて前
に進む姿が描かれている。
しかし、『きよしこ』は、それを読者に喚起させるも
のではない。
子を持つ親が、「子どもに読ませたい」と思う本…
と言って良いだろうか?
なんとなく重松氏にとっての原風景であり、作品
の原点を見たような気がする“お話”だった。
『きよしこ』
の子を持つお母さんから「励ましてあげてください」
という手紙をもらったことから“お話”は始まる。
結局重松氏はこの子に手紙を書くことはなかった
が、その代わり「個人的なお話」として、この『きよ
しこ』を書いて、少年に送ることになる。
どこまでが実体験かはわからない。
しかし、吃音を持つ少年の心を描いた、重松氏の
自叙伝的作品となっている。
主人公の少年は小さい頃から吃音を持ち、言い
たいことが言えずに育つ。
その上、父親の仕事で転校を繰り返すため、友だ
ちが出来ない。
心の中ではすらすらと喋れる言葉も、声にすると
「カ」行や「タ」行、濁音で始まる言葉が上手く言え
ず、最初の自己紹介の「キヨシ」でつまずいてしまう
のだった。
「・・・なんでも話せる友だちが欲しい」
「きよしこ」は、そんななんでも話せる、少年の空
想の中の友だちだ。
少年はクリスマスの夜にたった一度だけ出会えたこ
のきよしこから、大事なことを教わる。
「それが本当に伝えたいことだったら・・・伝わる
よ、きっと」
重松氏の得意な短編連作形式のこの“お話”は、
小・中・高校時代、部活動など、各年代で少年と
強く関わる人間関係が描かれているが、その一
話一話に少年の「本当に伝えたいこと」が散りば
められている。
最初は苛立ちや諦めが目立ち、読んでいて切な
くなったが、痛みを抱えながらも徐々に強くなって
いく少年や、少年を取り巻く人々になんとも暖かい
気持ちにさせられ、自然に涙がこぼれる。
また、少年がここぞという時に伝えようとする「思
い」のこもった言葉には感動させられた。
レビューなどには「障害のある方は是非一読を…」
みたいな言葉が見受けられるが、果たしてそう
だろうか?
健常者こそ読むべきだと自分は思う。
冒頭のお母さんが手紙に書いた「吃音なんかに
負けないで…」の“なんか”。
少年が嫌がったように、形だけの同情や憐れみ
は差別と変わらないのだと強く感じた。
もちろん、この本が言いたいのはそういうことで
はないだろうが…
さて、先の『流星ワゴン』で書いたように、この『きよ
しこ』もまた最後に救いが…現実を受け入れて前
に進む姿が描かれている。
しかし、『きよしこ』は、それを読者に喚起させるも
のではない。
子を持つ親が、「子どもに読ませたい」と思う本…
と言って良いだろうか?
なんとなく重松氏にとっての原風景であり、作品
の原点を見たような気がする“お話”だった。
『きよしこ』
Posted by ug at 08:33│Comments(3)│ほんのはなし
この記事へのコメント
さすが!って感じのレビューですね(^^)
Posted by you at 2008年09月16日 10:32
↑すみません、改行したつもりが、
書き込まれちゃいました(^^;)
『きよしこ』お借りした当日読了
しました。よかったです。
子を持つ親として、すごく身に沁
みる話でした。
長女はもうすでに友人関係で悩む
ことも出てきているので、障害が
あるなしに関わらず、親として読
んでおいてよかったと思いました。
って、言うか前から読みたかった
ケド、金欠で買えないだけだった
んですが(^^;)
日曜には『きみの友達』も一気に
読了!こちらもよかったです!!
今は『みぞれ』を読ませていただ
いてます(^^)
もうしばらく、お借りしますね♪
書き込まれちゃいました(^^;)
『きよしこ』お借りした当日読了
しました。よかったです。
子を持つ親として、すごく身に沁
みる話でした。
長女はもうすでに友人関係で悩む
ことも出てきているので、障害が
あるなしに関わらず、親として読
んでおいてよかったと思いました。
って、言うか前から読みたかった
ケド、金欠で買えないだけだった
んですが(^^;)
日曜には『きみの友達』も一気に
読了!こちらもよかったです!!
今は『みぞれ』を読ませていただ
いてます(^^)
もうしばらく、お借りしますね♪
Posted by you at 2008年09月16日 10:41
>>youさん
読むスピードが凄すぎます、あなた。
それでは確かに“ミニ”図書館では間に合いませんね。
とにかく蔵書数の多い図書館を作ってもらいましょう!!
読むスピードが凄すぎます、あなた。
それでは確かに“ミニ”図書館では間に合いませんね。
とにかく蔵書数の多い図書館を作ってもらいましょう!!
Posted by 代表ug at 2008年09月17日 19:11
at 2008年09月17日 19:11
 at 2008年09月17日 19:11
at 2008年09月17日 19:11コメントフォーム